スペイン砦、屋上階――。
いつしか辺りは日が傾きはじめ、空は茜色に染まりはじめている。
血のような紅味を帯びた陽を受けながら、スペイン軍総指揮官アレッチェは、火の海と化した洋上を冷やかな横顔で睥睨していた。
彼の両脇に累々と並ぶ要塞砲は、止め処なく火を噴き続けており、その硝煙と洋上からの攻撃によって噴き上がる黒煙とに阻まれ、視界は色濃く霞んでいる。
黒々とした髪が不意に爆風に煽られ、彫の深い造形が露わになった。
その輪郭の中で光る黒眼には、非情なまでに感情が見られない。
煙霧に霞んだ向こうに見下ろせる洋上では、英国艦もスペイン艦も、炎に包まれ、既に撃沈されているものも少なくない。
だが、まだ生き延びている英国艦とスペイン艦は、即席の「連合」艦隊と化して、粘り強い反撃を続けている。
撃沈された艦があるのみならず、まだ生き永らえている艦たちとて著しく破壊され、両艦隊を合わせれば本来は千門を遥かに超えていたはずの艦砲も、その数を大きく減じていた。
にもかかわらず、数百に及ぶ艦砲は今も火を噴き続け、この砦の側面を叩きつけている。
(なんたる執念深い奴らだ――)
砦の石壁にのめりこむ砲弾の振動を足下に感じ取りながら、砦の受けている打撃をさらに推し量るかのように、アレッチェの硬い靴底が忌々しげに石床を踏みにじる。
洋上からの艦砲射撃の射程はこの屋上部の要塞砲までは至らぬとはいえ、当初は砦攻撃を拒んでいたスペイン艦までもが、ついに同胞のこの砦に発砲を開始したことで、砦の基底部や中腹部が受ける打撃は増大していることは明らかだった。
(裏切り者どもめ…!
昨日の英国艦隊との海戦で、あれほどの惨敗を舐めただけではあきたらず、むざむざ捕虜にされた上に、英国艦隊に与(くみ)して味方の砦に攻撃まで行うなどと。
ただ黙って、自沈することさえできぬのか)
その氷のような酷薄な面差しを部下に振り向け、アレッチェが冷たく言う。
「あのような瀕死の艦隊に、いつまで手こずっている。
沈みかけの図体で砲撃を続けてきおって、往生際の悪さには驚かされる。
いい加減、奴らの攻撃を黙らせねば、こちらの身ももたなくなるぞ。
その上、日も暮れてきた。
このままでは、夕闇に紛れて砲撃が難しくなる上、あの者どもを取り逃がすことにもなりかねぬ。
そうさせぬためにも、攻撃をさらに強め、もっと加速させろ。
一艦の退却の隙も与えることなく、一刻も早く全艦を撃沈させるのだ」
「はっ!」と恭順を示してから、しかし、アレッチェの命を受けた部下が、言いにくそうに、組み合わせた手を擦り合わせた。
「とはいえ、閣下、い、いえ、その…やはり――スペイン艦も全艦撃滅と……?」
苦渋の滲む表情を隠しきれぬ部下を、険しく吊り上がったアレッチェの両眼が、射るように睨(ね)めつける。
「あれらのスペイン艦の乗員には、もはや戻ってくる場所など無い。
洋上で散らしてやるのが情けというものだ」
ただでさえ硝煙と砲煙にけむる洋上の視界は悪い上に、着実に降りくる色深い夕闇。
さらに、この砦自体も、自らが放つ無数の要塞砲が吐き出す硝煙と、艦隊から受ける攻撃による砲煙とに押し包まれ、いっそう視界は閉ざされている。
それらの黒煙や濃さを増す夕闇によって、ますます霞みゆく大海原を睨み据えるアレッチェの背後から、けたたましい警笛の音と共に衛兵の叫び声が響いてきた。
こちらの海側方面とは反対面、砦の山側方面を警護している衛兵たちの声である。
「あれは、インカ軍です!!
インカ軍が、こちらに向かってきます!!」

アレッチェは、殆ど反射的にそちらを振り向いた。
それと同時に、現在、この砦でアレッチェの側近を務めるサルセード大佐が、恰幅のいい全身をゆさゆさ揺らしながら、慌ただしくこちらに駆けてきた。
「閣下、インカ軍の襲撃ですぞ!!」
壮年のサルセードの薄くなってきた頭と広い額が、沈みゆく夕陽を反射して、場違いなほどテラテラと眩く照り映えている。
そのサルセードが重そうな体を上下させながら息を切らしている姿から、不快なものでも見るようにアレッチェは視線を引き剥がした。
それから、「チッ」と、石床に唾を吐きつける。
「英国艦隊に、もう一息で止めを刺せたものを」
憎々しげに低く言い捨てると、海側とは反対側の山側方面へと足早に屋上階を横断していく。
その後を、豪贅な脂肪を揺らしながら、サルセード大佐が大儀そうに追いかける。
この砦は、主として、当植民地を狙う海からの外敵の侵入に備えて築かれたものであるため、屋上階の主砲台は海側に面している。
しかし、当然ながら山側からの攻撃にも備えられており、同じ屋上階には、山側方面にも多数の砲台が据えられていた。
とはいえ、此度の英国艦隊を迎え撃つために、山側砲台に据えられていた要塞砲も全て海側砲台に回し、砦の全砲をもって敵艦隊に砲撃を加えていたのだった。
今、山側からインカ軍の襲撃が開始されたとなると、それらの要塞砲群の中から、山側砲台の分を元の位置に戻さなくてはならない。
つまるところ、英国艦隊の撃滅に用いていた要塞砲が減じられることになるのだ。
忌々しげに舌打ちして、アレッチェが砲主長に一瞥を投げた。
「山側砲台の要塞砲を所定の位置に戻せ」
「はっ!!」
砲主長が指示に従うため走り去っていくのを背後に聞き取りながら、アレッチェは、山側砲台の中央部に進み出た。
その屋上階の砲台中央部から、砦の下方を覗き見る。
見下ろす石壁のちょうど真下付近には、この砦の正門が堂々と構えられている。
砦の出入り口は山側に面したこちら側のみに築かれており、敵襲に備えて、今は厳重に閉ざされている。
対して、海側には、切り立った断崖絶壁上にある建造物の構造上、出入り口は造られていない。
砦側からの攻撃は海陸双方向に対して可能な上、敵の侵入経路は山側の正門一ヶ所に限定されており、攻撃に強く守りに堅い構造となっているのだ。
今、山側に面した屋上階に立つアレッチェのがっしりした長身を、沈みゆく夕陽が血の色に染め上げていく。
眼下に広がる砦の山側裾野には、ところどころ森林や低木のおい茂る樹林地帯が散在するも、概ね乾いた砂漠や荒野が広がっている。
それらの荒れ野の果てには、紫紺色にけむるアンデス山脈の連綿たるシルエットが見晴らせる。
砂漠広がる海岸地帯、霊峰連なるアンデス地帯、深い密林に覆われたジャングル――この植民地の大地も植生も、産する鉱物も、何もかもが実に多彩で欲望をそそられる。
これまでも、莫大な富、絶大な権力、圧倒的な名望、己が手にした全てを、この最果ての植民地が与えてくれたのだ。
(この地からは、まだまだ絞り取れるものがある。
あの蛮族どもの手に奪還させるなど、及びもつかぬことだ)
まだ夕陽の明かりが淡く残る海側とは異なり、この反対面の山側は、既に夕闇に閉ざされつつあった。
その濃さを増しゆく荒野の薄闇の向こうから、ほどなく朱色に輝く多数の光が見えてきた。
進軍するインカ兵たちが掲げる松明(たいまつ)の炎に相違ない。
それらの煌々たる光の帯が、たちまち量感を増しながら、炎の大波が押し寄せるがごとくに迫り来る。

一方、砦の最上階では、背後の海側で火を吐き続ける要塞砲の殷々たる砲撃音が今も鳴り続く中、山側の要塞砲を守備する兵たちが、こちらでも迎撃態勢を着々と整えていく。
それらの兵たちの良く訓練された動きを目の端に感じ取りながら、荒野を向いたままのアレッチェが、脇のサルセード大佐に抑揚の無い声で低く問う。
「で、こちらに向かってくるあの軍勢を率いているのは、トゥパク・アマルか?」
サルセードが、たぷついた頬を振った。
「いえ、偵察隊の話しでは、もっと若いやつだったとか」
「若いやつ?」
「はい、閣下。
報告された身なりや背格好からは、あのアンドレスとかいう、若い将兵ではないかと思われます。
斥候の報告からも、当地に布陣するインカ軍を指揮するトゥパク・アマルの副将は、アンドレスと聞き及んでおります。
トゥパク・アマルは、まずはアンドレスを進軍させて、我らの出方を見ようというのではないでしょうか?」
サルセードの答えが終わるのを待たず、アレッチェは手近にあった望遠鏡を掴み取ると、無言のままに片目にあてがった。
薄闇の中では望遠鏡の視界もききにくかったが、赤々と燃える松明を掲げた人山の黒だかりが、ますます勢いを増して押し寄せてくる。
そのおおよその規模や様子は、望遠鏡を介した夜目ながらも、それなりに見て取れた。
規模は驚くほどではなく、せいぜい兵力700〜800程度か。
騎兵はおらず、革鎧で武装した歩兵ばかりの軍団。
だが、隊列の動きは、かなり統制がよく取れており、それでいて、非常に敏捷だ。
さらに、野戦砲を載せた多数の重々しい台車が、ひときわ大柄で厳ついシルエットを持つ兵たちによって、ガラガラと勢いよく引かれてくるさまも見て取れる。
それらのインカ軍歩兵部隊をくまなく見渡してから、さらに、その軍勢の陣頭中央部へと、アレッチェの望遠鏡は動いていく。
陣頭に立って、猛々しく雄叫びを上げながら、褐色の兵たちを鼓舞しているのは、確かに若いインカ兵のようだった。
視界が悪く、その者の顔形などの細部までは判別できない。
が、若々しく逞しい肉体に銀糸の刺繍の施された漆黒の戦闘衣と分厚い胸甲を纏い、いかにも重厚そうな剣を携え、黒の短マントを翻すその姿は、先のサルセード大佐の言葉通り、これまで戦場で幾度も見かけてきたアンドレスの恰好に他ならなかった。

若者のシルエットが、ザッと、剣を握った腕を高く振り上げ、鋭く何か号令を叫んだ。
その号令に呼応して、押し寄せていたインカ軍は、砦からの砲撃の射程圏内に入る手前で、ピタリと進軍を止めた。
その位置は、昨日、砦のアレッチェとの小競り合いの際に、トゥパク・アマル自身が自らの身をもって感得していた場所であった。
正確に伝授されたその位置から、今、砦と対峙しつつ、長大な砦の長さいっぱいに広がり、迅速に戦闘隊形を組み直していくインカ軍の淀みない動き。
と同時に、彼らが運んできた多数の野戦砲が、台車ごと隊列の最前列に引き出されてくる。
さらに、それらの最前列の野戦砲の背後にも、もう一列、新たな野戦砲の隊列が整然と並べられていく。
砦の長辺に添って、累々と並べられていく野戦砲の二列横隊。
そして、野戦砲の縦隊の背後に決然と隊列を成す、褐色の若き歩兵軍団。
砦の屋上階で、それらインカ軍の一連の動きを値踏みするように見据えたまま、アレッチェがサルセード大佐に低く言う。
「どうやら向うの準備も整ったようだ。
そろそろ迎えの砲撃を見舞って、あの者たちを歓迎してやるがいい」
「はっ、閣下!
ただちに!!」
他方、インカ軍の方でも、陣頭に立つ若者が険しい目で砦を見据えながら、号令を発していた。
「野戦砲部隊、前後列共に砲撃準備!!」

陣頭指揮を執るその若者――それは、アンドレスと同じ戦闘衣を纏ったロレンソであった。
アンドレスとは学生時代からの朋友であり、志を同じくする戦友。
且つまた、トゥパク・アマルの信頼を得て、アンドレスと同様に、若くして反乱軍を統率する将兵の一人でもある。
インカ軍に結集した義勇兵や専門兵たちの多くの若武者たちは、概ね、このロレンソやアンドレスの連隊に属しているといっていい。
外見的にも、アンドレスと同年齢の彼は、長身の背格好や肩先で切り揃えられた髪型など、遠目からはアンドレスとよく似ていた。
だが、傍近くで見れば、スペイン人との混血児であるアンドレスと比べて、生粋のインカ族たるロレンソは、肌の褐色も濃く、髪も漆黒で直毛。
その風貌はインカ族らしい野性味と鋭利さをもち合わせ、加えて、インカ貴族らしい気品をも兼ね備えている。
「さあ、皆、待ちに待った我らの出番だ!
存分にスペイン軍のお相手をしてやれ!!」
剣を振りかざし猛々しく言い放つロレンソに、彼の率いる鋭気漲る若きインカ兵たちが、「オー!!」と、勇壮な鬨の声を上げて呼応する。
それらの兵たちの熱く高まった闘志を凛々しい眼差しで見渡しながら、その一方で、ロレンソの表情は、彼特有のひときわ沈着な冷静さをも失ってはいない。
自軍の兵を鼓舞しながらも、同時に、自軍の兵を牽制する――その難しい任務を果たせる者として、平素の動向や性格を踏まえ、トゥパク・アマルが抜擢したのが、このロレンソであった。
こうしてロレンソが敢えて「アンドレス」に扮しているのは、砦のスペイン軍の注意をロレンソの連隊に引き付け、別の場所から砦攻略に挑むアンドレス隊のために時間を稼ぎ、彼らの作戦遂行を援護するためである。
実際には、今頃、本物のアンドレスや彼の率いる部隊は、砦の反対側――つまり砦の海側の麓付近にいて、そちら側から砦に侵入する方法を画策しているはずである。
さらにまた、ロレンソが「アンドレス」に扮しているのは、この「副将アンドレスの連隊」の動きを背後で見守っているトゥパク・アマルの大隊も含め、全てのインカ軍主力部隊が砦の正面側にいると、アレッチェに思い込ませるためでもあった。

「前列、撃て!!」
インカ軍の第一列目の野戦砲と、そして、スペイン砦の要塞砲が、同時に、長大な横一閃、眩い朱色の光に瞬いた。
濃さを増す夕闇の中、双方の大砲が、一斉に火を噴いたのだ。
割れるような轟音が大気を引き裂き、大地震のごとき地鳴りと衝撃波が大地を揺るがす。
砦の麓に陣取るロレンソ軍を呑み込むように、茫漠たる黒煙と砂埃が地に吹き荒れた。
が、同様に、砦の山側石壁もまた、濃い煙霧に覆われていく。
ロレンソは、砦の射程外であることを慎重に計った上で陣を敷いたつもりであったが、想定された以上に射程が伸びた砦からの砲弾の一部が、自軍の隊列前線に幾つかの無残な空隙を掘っていた。
「負傷兵を救出しろ!!
合わせて、隊全体、もっと砦の射程の外まで退がれ!!」
負傷兵を運び出させつつ、自軍の前線を砦のさらに射程外まで注意深く後退させながら、ロレンソは唇を噛み締めた。
その峻厳な眼差しが、ギリッと、砦を振り仰ぐ。
彼の視線の先で、砦の石壁もまた、予想以上に飛距離の伸びたロレンソ軍からの砲弾の幾つかに、深い爪跡を刻まれている。
昼間は海から吹きつけていた風も、今は凪ぎつつあり、少なくとも風の条件は互角。
それでも、高所からの砲撃が可能な砦側の方が射程も長く、有利な上、強壮な要塞砲の威力は、戦果として敵軍から奪った寄せ集めのインカ軍の野戦砲とは比にならない。
しかし、それでも、ロレンソは、自軍に属する鋭気漲る若き兵たちの、野性の敏捷性と強靭さ、その両者を兼ね備えた高度の運動能力及び身体能力は、必ずや、数段、スペイン兵より勝っていると信じて疑ったことはない。
装てんから発砲に至るまでの一連の動作は機敏で無駄が無く、照準を合わせる精度も、それに伴う命中確率もかなり高い。
長い反乱期間を経過してきたここまでに、実戦と訓練も十分に積んでいる。
実際、一部ではあるものの、このような射程外の場所からさえも、堅固な砦の石壁に命中弾を浴びせることができているではないか。
だが、その一方で、ロレンソは、己の心の奥底でウズウズと蠢く別の思いを感じてもいた。
(さりとて、さらに砦の射程から逃れるように前線を下がらせた今、ここから砦に砲弾を命中させるのは、もっと難儀になった…!)
夕刻の風に吹き上がる硝煙と砂塵を無造作に左腕で払いのけ、ロレンソは、自分と同様にジリジリ堪えている自軍の兵を素早く見渡し、奥歯を噛んだ。
高い志と戦意に燃える若者たちにとって、敵の総大将を目前にしながら、後退させられ、待ったを喰らわされるのは、無謀な突撃を敢行させられるよりも耐え難いに相違ない。
(だからこそ、指揮を任された自分こそが、断固として自制しなければならないのだ…!
わたしが突っ走ったら、皆、歯止めがきかなくなる。
口惜しいが、あくまでここから、あくまでこの場所からの攻撃しかない)
そう強く言い聞かせて己を戒め、ロレンソは、また高々と掲げた剣を力強く振り下ろした。
「第二列砲撃部隊、撃て!!」
再び轟き渡るロレンソ軍の砲撃音、そして、大地を揺るがす衝撃波。
射程外からの砲撃なれば、多くの砲弾は、砦の石壁を撃ち据える前に虚しく地に落ちていく。
本来ならば、第一列砲撃部隊と第二列砲撃部隊とを交互に駆使して、間断無い連続斉射を行いたいところであったが、こうも目標から遠くては、それを行えば無駄に貴重な砲弾を浪費することになる。
いっそのこと、思い切って野戦砲の射程内まで砦に肉薄し、これまで訓練してきたように猛スピードの波状攻撃を断行すれば、たとえ頭上から敵弾を被ることになろうとも、それ以上の大きな打撃を相手に与えることができるのではあるまいか。
(ここにいる兵たちなら、必ずや、勇敢に戦い切るだろう!
己自身や当軍の兵が犠牲になろうとも、結果、インカ軍の勝利につながるのならば――!)
背後で身構える兵たちも、もっと前へ出ましょう!!と、燃えるような眼差しで己に激しく訴えているのが伝わってくる。
ロレンソの右足が、ぐっと、一歩、大きく前に踏み出した。
『――ロレンソ、ならぬ!!』
その刹那、耳奥にトゥパク・アマルの厳然たる声が聞こえた気がして、ロレンソは、ハッと我に返った。
(トゥパク・アマル様……!)
強度に火薬臭い硝煙の中で、彼は逸(はや)りかけた己の心を抑え、踏み出した足を地面から引き剥がすようにして元に戻した。
今一度、ロレンソは、為すべきことを冷徹に反芻する。
(トゥパク・アマル様、分かっています!
これは、あくまで作戦全体の一部であって、今は敵の注意を引きつけ、時間を稼ぐことこそが肝要なのだと。
それに、甚大な犠牲が出ることが分かりながら、兵を突撃させることなどいたしません)
インカ軍本陣を出陣し、アンドレスと二手に分かれて、それぞれの場所からスペイン砦と英国艦隊の戦況の成り行きを見守っていたロレンソのもとに、トゥパク・アマルからの指令が届いたのは、つい先ほどのことだった。
あの時に伝令の兵が伝えたトゥパク・アマルの言葉が、今再び、トゥパク・アマル自身の声となってロレンソの心に甦る。
『ロレンソ、そなたの軍は、砦の背面から侵入を図るアンドレスたちを援護してやってほしい。
そなたは砦を正面から攻め、スペイン軍の注意を引き付けよ。
そうすることによって、砦からの激しい集中砲火を浴びて壊滅寸前の英国艦隊を援護することにもなろう。
我らは、英国艦隊に与(くみ)するものではないが、今の状況では、恐らく、砦からの砲撃の苛烈さゆえ、英国艦隊は撤退をはかる隙も見いだせないものと思われる。
英国艦隊も我らにとっては敵軍とはいえ、むやみに多数の人命を奪うことは、我らの願うところではない。
そして、それは、そなたの率いる軍にも言える。
そなたは、あくまで、スペイン砦の戦力を分散させ、その注意を引き付けることができればよい。
砦の要塞砲による火砲の威力は、我らなどに及ぶものではない。
増してや、砦の上方から撃ち込まれくる敵の砲撃の射程は、地上から迎撃するそなたの軍の射程よりも遥かに長大だ。
故に、決して前に出すぎるな。
あくまで、果敢に砲撃をしかけていくように見せかけ、時を稼げればよいのだ。
そなたの軍の若き兵の命を最大限に守ってやってほしい』
他方、自軍の射程圏内に入ってこようとしないインカ軍の若武者たちを砦の屋上階から睥睨しながら、アレッチェは、石の手すりを、カッ、カッ、と爪先で規則的に弾いている。
(青二才の臆病者めらが、何を尻込みしている。
若者どもらしく、もっと意気盛んに、思い切った攻撃をしてくればよいものを)
冷たく硬い手すりを弾くアレッチェの指先に、苛立ちが募っていく。
あくまで砦の射程圏外にいながらも、こちらを険しく睨み据えるように隙無く俯角をつけているインカ軍の野戦砲群からは、今も猛々しい闘志が漲り渡っている。
そのさまからも、眼下のインカ軍が射程内に入ってこない理由が、恐怖心からなぞではないことを、実のところは、アレッチェも察してはいた。
(これが、本当に、あのアンドレスの率いる軍か?
血気に逸ったあの若造ならば、もっと早々に無謀な肉弾攻撃を仕掛けてきていそうなものだ。
――だというのに、此度は、妙に自制がきいている)
前髪の陰から覗くアレッチェの濃い眉が吊り上がり、その黒眼が酷薄な光を強める。
(この反乱期を通じて、我らスペイン軍は、かえってインカ軍に戦い方を教え、皮肉にも兵士として育ててきてしまったのかもしれん。
トゥパク・アマルを葬り去るのはもとより、先々の植民地支配の安寧のためにも、このような若芽は、ここで完全に刈り取っておかねばなるまい)

眼下のインカ軍を睥睨しながらアレッチェが思い耽っている背後から、サルセード大佐が、慌ただしくドタドタと石床を踏み鳴らして、こちらに駆けて来た。
「閣下、英国艦隊が、退却していきます!!
インカ軍への砲撃に回した分の武力が弱まったのをいいことに、それに、夕闇が降りてきたのに身を紛らせて、逃げ出していきます!!」
アレッチェの手が、バシィッと、手すりの石板を叩きつける。
歯噛みしながら半顔だけ振り向いたアレッチェの目が、相手を刺し貫いた。
「撤退していく艦はどれほどだ」
「半数近くは撃沈しておりますから、その残りの艦が…!
捕虜のスペイン艦も数隻、沈没を免れており、それらも引き連れて去っていきます」
「ジョンストンの英国艦隊旗艦は、どうなった?」
「はっ…!
英国艦隊旗艦も、辛うじて生き延びていて、共に撤退を……!」
「――っ」
「要塞砲全砲を挙げて攻撃を続行しておれば、あやつらが退却する余地すら与えず、あの場に釘付けにしたまま全艦壊滅させることができたでしょうに。
実に口惜しいことです、アレッチェ様!!」
インカ軍に向き直ったままサルセードの報告を聞いていたアレッチェが、チッと、手すりの向うに唾を吐きつけた。
かたや、サルセードは、アレッチェの脇で、さらに捲し立てている。
「我らのスペイン艦隊が健在ならば、すぐにも追撃させるのですが、艦隊を丸ごと奪われた我らには、それもかなわぬことでありますし…!
ですが、閣下、英国艦隊の損傷はひどいもんで、あれでは、あの者どもの国に無事に帰還できるかどうかも怪しいところです。
増してや、あんな状態では、また我らの砦に戦闘を仕掛けてくるとは、到底、思えません。
英国艦隊旗艦につきましても、あれほどの集中砲火を浴びながら、ジョンストンが生き延びているかも甚だ疑わしいことですし――」
「舌をしまっておけ。
いらぬ憶測に何の意味がある」
アレッチェは冷やかに相手を遮り、「英国艦隊の再来に備えておけ」とだけ、吐き捨てた。
それから、こちらに狙い定めて今も闘志を露わにしている眼下のインカ軍を、憎々しげに睨(ね)めつける。
アレッチェの視線は、やがてロレンソたちの軍を通り越し、その背後に黒々と広がる闇の中へと動いていった。
(トゥパク・アマル、余計な邪魔立てをしおって…!)
サルセードを再び振り向いたアレッチェの目の端に、憎悪の光が強まっている。
「ここに押し寄せているインカ軍の雑魚どもを早々に我らの射程圏内に引き入れるのだ。
射程内に入った雑魚どもが我らの砲火で滅多打ちにされているのを見れば、未だに高みの見物を決め込んでいるトゥパク・アマルも、看過できずに炙り出されて現れてこよう」

対して、その砦を前にして、今も射程圏外に頑として踏みとどまるロレンソ軍。
まるでトゥパク・アマル軍本隊と砦との間の盾となるかのように布陣した、その若き軍団の最前線で、隊長ロレンソは砦の屋上階を鋭い眼差しで見上げていた。
そんなロレンソの元に、全力疾走してきたものと思われる伝令の兵が、息を荒げながらも生き生きと瞳を輝かせながら報告する。
「ロレンソ様!!
英国艦隊は、全滅を免れ、生き残った艦は退却していきました!!」
「そうか!!」
ロレンソも表情を大きく輝かせる。
その瞬間、またも、砦の要塞砲が一斉に火を噴く音が、轟然と響き渡った。
十分な射程圏外にいるロレンソたちの部隊まで、それらの敵弾が届くことはなかった。
が、それでも、地面をえぐって降り注ぐ砲弾の巻き起こす猛烈な砂煙と震動が、ロレンソ軍に大波のように襲いかかる。
むせ返りながらも砂塵を荒々しく払いのけ、鋭利な眼光を利かせながら、若き兵たちがロレンソの意志と連動するかのように、即座に砲撃態勢に入る。
それらの兵たちの我が身と一心同体な動きに力強く頷き返したロレンソの剣が、白銀の閃光を放って宙を掻っ斬った。
「第二列砲撃部隊、撃て!!」
深々と降りた夜の帳を引き割るように、インカ軍の砲口群が横一線、カッと、朱紅に瞬いた。
と同時に、勢い良く飛び出した鉄弾たちは、しかしながら、その多くは射程外の砦に到達する前に地に落ちていく。
分かっていても、その弾道を追うロレンソたちインカ兵の胸は、またも口惜しさと虚脱感に覆われていく。
その時である。
砦の屋上階に灯る幾つもの松明の間から、不意に、ガッシリした長身のシルエットが浮かび上がったのだ。
遠目ながらも最高位のものと分かる軍服、さらに、その人物の纏う雰囲気や体格、朧ながらも炎に照らし出された冷徹な風貌からも、それが敵将アレッチェ自身であると、ロレンソには瞬時に分かった。
先刻からずっと、あの手すり際にいたのか、あるいは、たった今、そこに現れてきたのか分からない。
いずれにしても、今、アレッチェの周りに松明が集められ、敢えて、その姿を鮮明にそこに浮かび上がらせているのだった。

「アレッチェ……!」
ロレンソは、反射的に、グッと、剣の柄を握り締める。
その力の激しさに、指の関節が白く浮かび上がった。
一方、焼け付くように睨み上げるロレンソの視線を受け、その視線の主を探るようにして、アレッチェの冷厳な黒眼が砦の麓を睥睨する。
彼の双瞼の中に捕えた、漆黒の戦闘衣を纏った陣頭の将兵――その若者の全身を、仄蒼く光るオーラが厚く押し包んでいる。
その姿を探り当てたアレッチェの目尻が忌々しげに聳やかされ、対して、彼の口端には、嗜虐的な笑みが浮かぶ。
火明かりを受けて赤黒く染まったアレッチェのシルエットが、夜の冷気を貫くように高々と叫んだ。
「そこの臆病者集団を率いている者、アンドレスよ、聞け!!
我々から盗み取った大砲を恥ずかしげも無く並べ立て、猿真似の弾撃ちを見せられるだけでも、見苦しきこと、この上無い!
その上、そのような屁っぴり腰で、しかも、そのような遠方に引っ込みながらの砲撃とは、及び腰にもほどがあろう!
これまで幾多の戦場で、インカ軍の見るに堪えぬ砲撃を目の当たりにしてきたが、おまえたちのような呆れた砲撃は、その中でも最低だ!!」

「――っ!」
険しく吊り上がったロレンソの目元が、ビリッ、と痙攣する。
砦とロレンソ軍との距離は、肉声が鮮明に聞こえるほど近くはない。
それでも、夜風に乗って、途切れ途切れに響き来る断片的な単語の一つ一つから、アレッチェが何を言っているのかは、容易に見当がついた。
ロレンソが己の身内に突き上げる激情を懸命に押さえ込んでいる間にも、彼の背後で次なる砲撃に身構えていた若武者たちが、「なにを!!」とばかりに、猛然といきり立ってどよめきを上げた。
それを、ロレンソが、すかさず制する。
「落ち着け!!
みえすいた挑発だ!!
それに、今のアレッチェ言葉をよく聞いたか?!
あの者は、我らの狙い通り、我々をアンドレスの――いや、アンドレス様の軍だと勘違いしてくれているではないか!」
「ですが…!!
あのような侮辱を受けて、黙っていろと言うのですか?!」
「挑発だと言っておろう!!
断じて、乗せられてはならん!!」
かたや、砦の上からは、アレッチェが、いよいよ皮相感たっぷりに続けていく。
「だが、おまえたちよりも、もっと臆病なのはトゥパク・アマルだ!!
おまえたちのような軟弱な雑魚どもを最前線に押し出して、この期に及んでも、未だ遠く背後に引っ込んだまま、コソコソと身を隠していようとは!!」
そのアレッチェの言葉に、砦のスペイン兵たちから、ドッと、大喝采が弾けた。
「そうだ、そうだ!!」と叫び、やんやと囃(はや)し立てる。
中には、口汚い罵声を上げる者や、下卑た口笛をピーピー吹き鳴らして揶揄する者までいる。
「あいつら、陛下に何たることを!!」
「絶対に――絶対に、聞き捨てならん!!」
己の周りでインカ兵たちが、いよいよ殺気だって口々に怒声を上げ、奔流のように砦に押しかけんとするのを、そこを通すまいと水平に両腕を振り上げながら、ロレンソが厳しい口調で一喝する。
「落ち着け!!
挑発だというに!!」
「ですが、あれほどまでに罵倒されながら、大人しくしていては、かえって陛下の御名と御名誉を傷つけることになります!!
あのように口汚い言葉で穢されて、素知らぬ顔を続けるなど――!!」
「くだらぬ挑発だ!!
分からんのか?!
我らを挑発して、砦の射程圏内までおびき寄せようとしているのだ!!
それだけではない!
我らを砲火の真下まで引き込み、奴らの砲弾の餌食となった我らをトゥパク・アマル様が救出に来るであろうと見越して――トゥパク・アマル様を奴らの射程圏内まで誘い出そうとしているのだ!!」
険しくも諭すように叫びながら、ロレンソは兵たちを必死で牽制する。
だが、ロレンソ自身の振り上げた腕もまた、止めようのない怒りと屈辱感に大きくわなないていた。
そのようなロレンソたちを、そこから暫しの距離を隔てた森林地帯で、出撃態勢を整えたインカ軍本隊の者たちが息詰めて見守っていた。
大軍の陣頭に立つトゥパク・アマルも既に愛馬に跨り、いつでも出撃できる態勢にある。
ありし日のインカ皇帝が愛用したのと同じ金糸の織り込まれた漆黒の戦闘衣に、分厚い革鎧を身に付け、足には銀の留め金を帯びた革製の戦闘ブーツを履いている。
そして、その腰には、重厚な長剣と厳つい銃が備えられていた。
次第に高くなる月光が樹間から斜めに射し込み、彼の胸にあるインカ皇帝の象徴、太陽を象(かたど)った黄金の首飾りを白銀に輝かせている。
逞しい白馬に跨ったトゥパク・アマルの傍を夜風が吹き抜け、端正な横顔を縁取る長い黒髪とビロードの黒マントを、緩やかに背後になびかせていく。

彼らのいるこの場所と砦の間には、まだ、かなり距離があるため、アレッチェが砦の上層階からロレンソに向けて何を言っているのか、その言葉を直接には聞き取ることはできなかった。
しかし、俊足の伝令たちがリレー形式で迅速に伝えてくる内容から、砦やロレンソ軍の様子は、ほぼリアルタイムに窺い知ることができた。
思慮深い横顔で伝令の言葉に耳を傾けていたトゥパク・アマルが、隣で黒馬に跨るビルカパサを僅かに振り向き、沈着な声で低く言う。
「さすがにロレンソ殿、この状況の中、よく堪えてくれている。
辛い思いをしておろうが、あの者なら、凌ぎ切るであろう」
「はっ、トゥパク・アマル様。
仰せのとおりと存じます」
鷲鼻の際立つ野性的な風貌を頷かせ、ビルカパサが答える。
平素から感情統制のいき届いたビルカパサらしく、今も、その表情は平静そのものだ。
が、それでも一言いわねば気が済まぬとばかりに、低く呻いた。
「それにしたって、なんたる無礼な輩(やから)でありましょうか。
いかに挑発せんがためとはいえ、トゥパク・アマル様に対しても、ロレンソ殿に対しても、あの言いようはあまりに」
周囲に控えるインカ兵たちも、尤もですと言わぬばかりに、憤然と鼻息を荒げた。
一方、トゥパク・アマルは、「そなたたちが挑発に乗ってどうする」と、切れ長の目元を僅かに細めて苦笑する。
それから、すぐに冷静な表情に戻って、褐色の長い指先で愛馬の手綱を握り直した。
「ホセ・アントニオ・アレッチェ――あの者は、やり手で、目的遂行のためには手段を選ばぬ冷酷さをも有している。
しかし、非常に誇り高い男でもあるのだ。
それを、いかに挑発のためとはいえ、砦のスペイン兵まで焚き付け、あのような如何にも低俗な言動を行うとは。
いささか、あの者らしくない」
ビルカパサの敏捷な視線が、サッと、トゥパク・アマルの横顔に走った。
研ぎ澄まされた面差しで前方を見据えるトゥパク・アマルを、月光を受けて鳶色に透けるビルカパサの瞳がじっと見つめる。
(アレッチェが、あのように下賤な態度にでているのは、ロレンソ殿が思うようにならぬ苛立ちもありましょうが、むしろ、それだけあの者の気が昂ぶっている証しでもありましょう。
あの者が貴方様を牢から取り逃がしてからの煩悶たる月日を想像すれば、ついに貴方様を捕え、あるいは、葬り去ることができる時が訪れたと思い決めて、興奮と喜悦を禁じ得ぬのではありますまいか)

ビルカパサがそのように思い巡らしている間にも、騎上のトゥパク・アマルは、隊長格の別の兵を振り向いて口早に問うている。
「陣営には、まだ実戦に臨むには早い訓練中の義勇兵たちが、少なからず残っていたと思うが」
「はい、陛下。
かなり訓練は進んでおりますが、まだ実戦に臨ませるまでには至らぬ者たちが、控えの兵として、数十名、陣営内にて待機いたしております」
トゥパク・アマルが敏捷に頷いた。
「それは助かる。
英国艦隊が去りし後も、海上には、沈没した英国艦やスペイン艦の残骸が、大小問わず無数に漂っている。
それらの沈没艦から投げ出された兵たちの中には、まだ生き延びている者たちがいるやもしれぬ。
ただちに我らの持てるありったけの小舟を出させ、陣営の待機兵たちに、海上で漂流している兵たちの救出に向かわせよ。
夜間の救出なれば難儀ではあろうが、朝まで放置しては、生存している者さえ息絶えてしまうであろう。
彼らを黙って見殺しにすることはできぬ。
英国兵も、スペイン兵も、存命の者は区別無く救出し、必要な治療を施すよう采配せよ」
トゥパク・アマルの言葉に、命を受けた兵は、深く恭順の礼を払った。
「はっ、トゥパク・アマル様、すぐにも!!」

かくして、トゥパク・アマルたちの見守る中、アレッチェら砦のスペイン兵の挑発にロレンソたちが堪えていた頃、正確には、その少し前だが、その砦の反対側――海側に面した砦の石壁の麓に、アンドレス軍の若き精兵たちがいた。
砦の石壁がそそり立つ狭い断崖際にいる彼らの遥か足下では、岸壁に荒々しく押し寄せる波濤が、打ち砕かれては、また押し寄せる音が絶え間なく続いている。
彼らは、濃さを増す夕闇の向うに、灰色がかった幾つかの帆影が吸い込まれるように消えていくのを見つめていた。
満身創痍の体を引き摺るようにして、日没の余映を微かに残した水平線へ溶けゆく英国艦隊のシルエット群。
その姿を、周囲の兵たちと共に、アンドレスもまた、まんじりともせず見守っていた。
沈没船や多くの破砕物で埋め尽くされ、凄惨な戦いの余韻が生々しく残る洋上からは、まだ強い硝煙の臭いが漂ってくる。
(ロレンソ!!
生き残った戦列艦たちが、去っていくぞ。
彼らが全滅を免れたのは、君たちが砦の戦力を分散させてくれたおかげだ!)
朋友の英姿を思って胸熱くするアンドレスの淡い褐色の頬を、栗色の柔らかな髪を揺らしながら夜風が吹きすぎていく。
ロレンソの怜悧な面差しを誇らしく思い出しながらも、同時に、その大切な友が、そして、彼の隊員たちが、今この瞬間も、あのアレッチェの毒牙の真正面に身を晒しているかと思うと、強く胸締め付けらずにはいられなかった。
作戦上のこととはいえ、ロレンソや彼に率いられた兵たちは、英国艦隊への攻撃から敵の注意をそらすためのみならず、ここにいる自分たちの行動から敵の目をそらさせるために、きわどい状況に身を投じているのだ。
しかも、ロレンソは、己の変り身を装っていさえする。
普段はアンドレスが着用している戦闘衣を纏ったロレンソに対して、今、アンドレス自身は、周囲の皆と同じ一兵卒の身なりに扮している。
アンドレスは、そんな自分の姿を見下ろし、大きな琥珀色の瞳を不安気に揺らした。
あのアレッチェが、最大のターゲットとしているのは、もちろんトゥパク・アマルだが、己自身もまた、あの者にとって、即座に抹殺したいと渇望している者の筆頭に挙げられるはずである。
それだけに、この自分の身代わりを演じるロレンソの危険は、いかに大きいことであろうか――。
アンドレスは、止め処なく膨れ上がる不安を吹き飛ばすように、ブンッと頭を振った。
(ロレンソは、俺なんかより、ずっとしっかりしている!
これまでも、いつだって、そうだったじゃないか。
今回だって、きっと、上手くやってくれるはずだ!)
こうしている間にも、さらに闇の深まる夜の大気の中で、アンドレスは頭上に聳え立つスペイン砦を大きく振り仰いだ。
その目元が、険しさを増す。
夜闇に呑まれて、昼間とは視界の利き具合は雲泥の差だ。
それでも、高々とした屋上階から海に向けて突き出された要塞砲の黒き砲頭群が、月明かりに照らされて白光りしているのが見て取れる。
今は沈黙を守っている海側の大砲群――先刻まで、洋上に向けて絶え間なく殺戮の炎を吐き出し続けていた大砲たちが、大仕事を成し遂げ、ひとときのまどろみの中に身を委ねている。
この砦のスペイン兵たちも、ロレンソの布陣する砦正面の山側砲台に多くが回っているのであろう、頭上の海側砲台は静けさに包まれていた。
対する砦の反対側、山側方面からは、断続的な砲撃音が殷々と響き渡ってくる。
互いの射程外から睨み合い、時に砲撃の応酬を続けるロレンソ軍とアレッチェ軍。
その一触即発の張り詰めた空気感を想像して、アンドレスは固唾を呑んだ。
(自制の利いたロレンソに、アレッチェは、さぞ苛立っていることだろう。
それだけに、あのアレッチェが何をやりだすか、気が気ではない。
ロレンソ…みんな……!)
再び胸締め付けられる思いにとらわれた彼の耳元に、声を落としながらも力を帯びた明るい声が響いてきた。
声の方を振り向けば、黒人青年ジェロニモが、白い歯を覗かせて笑みを見せながら、グーサインを送っている。
「アンドレス様!!
みんな、準備OKです!」
アンドレスも我を取り戻して、それに応じて元気に頷いた。
「よしっ、はじめよう!」
そのアンドレスの号令に呼応して、辺りの兵たちの多数の黒い影が、音もたてず敏捷に動き出す。
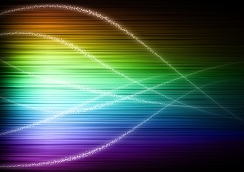
この場でアンドレスと行動を共にしているメンバーたちは、野性の運動神経を備えた若きインカ兵たちのみならず、実戦経験を積んできた黒人兵も多く、そんな彼らの動きは闇の中でも実に機敏だ。
スペインの植民地支配下で苦しんできたのは、決してインカ族の人々だけではない。
遥かアフリカの祖国から強制的に連れてこられた黒人の者たちも、その圧政下で、インカ族の者たち以上に苦しんできた。
そうした彼らの解放をも訴えて立ち上がったトゥパク・アマルのもとには、こうした黒人兵も数多く結集している。
そのような黒人兵たちの多くが、高度な運動神経を求められる此度のアンドレスの作戦に協力を求められ、この場に来ていたのだ。
今、彼らを率いて作戦行動に入ろうとしているアンドレスの足元の深い崖下では、荒々しさを増した夜の海が、大波を泡だてながら、獲物を待ち受ける魔物のように大口をバックリ開けている。
出入り口も設けられていない砦の海側麓には、本来は人が立つことなど無かろうために、砦の石壁と崖っぷちとの間に許された空間は、非常に狭い。
つまりは、かなり断崖渕ぎりぎりに砦が屹立している状態なのだ。
一歩でも動きを過てば、真っ逆さまに暗黒の海に落ち込んでしまいかねない。
アンドレスは、密かに、生唾を呑みくだした。
だが、黒人兵たちは臆する様子も見せず、その狭い崖っぷちの岩壁沿いに、堂々と広く散開している。
狭い地面を上手く使ってドッシリと仁王立ちになった大柄な兵たちの濃いシルエットが、月明かりに浮かび上がる。
それらの兵たちの中央付近に立ったアンドレスは、全体を見渡してから、意を決したように力強く頷き、「行くぞ!!」と大きく身振りで示した。
巨躯を備えた兵の高々とした肩へ、タンッ、と軽やかに飛び乗ると、その兵の援護を受けて、砦の石壁に取り付いた。
そのまま、両手両足で、壁を這い登りはじめる。
先陣を切って石壁を登りだしたアンドレスを追うようにして、他の兵たちも、彼らを援護する巨体の兵たちに投げ上げられるようにして、次々と壁を這い登りはじめた。

高さは優に30メートルはあろうか、その90度に切り立った石壁を、スペイン兵たちに気付かれる前に制覇せねばならないのだ。
かなり無茶な作戦ではあったが、さすがに敵兵たちも、この険しい石壁を登ってくる者たちがいるなどとは思っていないはず――そこに、僅かながらも勝機が生まれるかもしれないのだ。
ビッシリ隙間無く巨石を積み上げ、石膏で固められた石壁。
それを登っていくことなど、通常ならば、恐らく普通の人間には不可能であろう。
しかし、今は、先刻までの英国艦隊の粘り強い砲撃によって、石壁は蜂の巣さながらにえぐられ、多くの石組みが崩れかかって、石膏部分が露呈している箇所も少なくない。
アンドレスたちは、各々、ひときわ強度の高い短剣を腰に帯びており、素手では如何ようにも取り付く場所を得られない時には、短剣を石膏部に打ち込み、それを起点に登り進んでいった。
それにしても、いかに石壁が崩れかかって、登攀(とうはん)のための手掛かりや足場が多少なりとも得られやすくなっているとはいえ、実際に登りだしてみると、予想以上に難儀をきわめた。
いくら組まれた岩石部よりは柔らかい継ぎ目の石膏部とはいえ、左手で壁の割れ目につかまりながら、右手のみで石膏に短剣を打ち込むのは猛烈な筋力を要した。
やっとの思いで首尾よく打ち込めたとしても、それは、全体の作業の僅かな一歩でしかない。
右手で打ち込んだ短剣を起点に、懸垂の要領で全身を引き上げたら、さらに上方の壁の割れ目に左指を入れて体を固定し、打ち込んだ短剣を右手で引き抜いて、もっと上方の石膏部に打ち込む。
それらの動きに合わせて新たな足場を見つけては、また壁の割れ目や石膏部を利用して腕を固定し、さらなる足場を見つけて前進する――その際限の無い繰り返しに、気が遠くなる思いだった。
しかも、壁面を照らしてくれるのは、せいぜい月光の仄かな明かりぐらいのもので、視界もひどく利きにくい。
命綱があるわけではないために、下手に手足を踏み外せば、遥かな断崖下で大口を開けている真っ黒な海面に、たちまち呑み込まれてしまうだろう。
下を見るまいと思っても、耳奥で常に鳴り響く潮騒が、いやがうえにも下方で逆巻く海面を思い出させ、眩暈のような感覚を引き起こす。
(なんてこった…!
こんなにきついなんて、予想以上だ……)
くらつく頭を振って、懸命に思考を澄ませようとしながらも、アンドレスは内心でそう呟かずにはいられなかった。
夜の冷気の中にもかかわらず、滝のような汗が全身を流れくだり、随所でギザギザに突起した岩盤に引っかかれて、はやくも体中は引っ掻き傷だらけになっている。
その上、まだ戦闘の余韻の残る石壁は、被弾した砲撃の余熱を帯びていて、場所によっては、プレートの上の石焼き肉のように体を焦がした。
そんな壁の途中に這いつくばりながら、ゼーゼー息を切らし、それでも目指し続ける終着点――砦の屋上階を見上げるも、まるで天頂を目指すかのように果てしなく遠く思える。

アンドレスは、無意識に、ハアッと、深い溜息をついた。
それから、慌てて、周囲の兵たちに気付かれてはいまいか、辺りを見回す。
石壁の麓で見張りの目を光らせながら待機している一部の兵を除いて、皆、自分と同じように壁に取り付いて頑張っている。
己の迂闊な溜息に誰も気付いていないことに、アンドレスは、ほっと胸を撫で下ろした。
(俺がしっかりしなきゃ、ダメじゃないか!
敵兵たちに気付かれてしまう前に、一刻も早く登りきらなければならないんだ)
アンドレスは、さらに大きく頭を振って汗の雫を振り払い、ぐっと腕に力を込めた。
幸い、今ではすっかり夜の闇に呑み込まれ、砦の上階から軽く下を覗き見た程度では、眼下に切り立つ石壁を登っている者たちがいるなどと、敵は気付きはしないだろう。
だが、明かりでも手にして深く覗き込まれたら、きっと、ひとたまりも無いに違いない。
それに、こうして石壁を登る自分たちから敵兵の注意をそらそうと、アレッチェと対峙し続けているロレンソたちの危険は、時間が経過すればするほど、ますます高まるのだ。
(あのアレッチェのことだ、何をしでかすか分かったもんじゃない!
それに、俺たちの行動が遅れれば、それだけ、トゥパク・アマル様たち本隊の皆にも、危険が増してしまう)
そう心は激しく急(せ)くものの、とはいえ、まだ全体の4分の1ほども登れていないのに、これほどまでに消耗している現実を思うと、絶望的な思いにとらわれる。
「くそ…!
気弱になっている場合か……!」
アンドレスは、奥歯を喰い縛った。
石壁の随所には、砦の覗き窓のようなものがついているのだが、英国艦隊が去ったためなのか、夜間だからなのか、あるいは、外敵の侵入を警戒してなのか、いずれの窓も鉄扉が固く下ろされ、内側から錠がかけられている。
(これが開いていれば、屋上階まで登らなくても、この窓から内部に侵入できるのに!)
また落胆しながらも、一方で、アンドレスは思い直したように、一人、心内で呟いた。
(いや、こんな覗き窓が開きっぱなしだったら、俺たちの方こそ、簡単に見つかってしまっただろう。
むしろ閉まっていてくれて、ありがたいことなんだ。
それにしたって……)

トゥパク・アマルたちと作戦を練っている段階でも、この登攀のハードさは想定内ではあったが、実際に登ってみると、その予想を上回るキツさ――。
(みんな、大丈夫なのか?!)
運動神経や体力には、そこそこ自信があるはずの己が、これほど辛いのだ。
アンドレスは、水を浴びたように噴き出す汗でベッタリ額にはりついた前髪の隙間から、不安げに周囲を見渡した。
(えっ?!)
目を瞬かせたアンドレスの前を、数名の黒人兵たちが、器用に岩山を登る野性の動物さながらに、崩れた壁の窪みを拠点に、さらなる窪みから窪みへ、スッ、スッ、と登り進んでいく。
苦戦しつつも先頭を登っていたアンドレスであったが、彼らは笑顔を向けて、「アンドレス様、一足お先に!」と身振りで礼を払い、軽やかに追い越していく。
「あ、ああ!
敵兵に勘付かれないよう気を付けていけよ!
上の方まで上がったら、まだ砦には乗り込まず、待機していてくれ。
そうだ!
あとロープを――」
息を切らしながら言いかけたアンドレスに、黒人兵たちは軽く振り向き、「分かってます!」と、肩に提げたロープをヒョイと片手で持ち上げて見せた。
そのような黒人兵たちの額にも汗が伝い流れ、息もそれなりに上がっていて、この急峻な岩壁を登るのに全く難儀していないわけではなさそうだったが、それでも、彼らの動きは、自分などとは比較にならぬほど敏捷だった。
「すげえなぁ…!」
思わず感嘆の声を漏らしながら、アンドレスが恍惚と呟く。
そんな様子を見ていた周囲のインカ兵たちも、負けじとばかりに発奮して登りだした。
アンドレスも気合を入れ直して、再び壁の割れ目を探して腕を伸ばした。
そして、ひび割れに突っ込んだ左手に、ギュウッ、と力を込める。
その時、サッと、見慣れた黒い影が隣で大きく手を振った。
「それじゃ、ダメダメっ!
アンドレス様は、手に力を入れすぎなんですヨ!」
声を低めながらも明るく囁いたその人物を振り向けば、いつの間に傍に来ていたのか、馴染みの黒人青年が朗らかに笑っている。

それから、その黒人兵は、突然、パッと両手を壁から離して、パタパタと宙で両腕を羽ばたかせて見せた。
「わあっ!!
やめろ、ジェロニモ!
落ちるぞ!!」
仰天して声を上げたアンドレスに、黒人青年ジェロニモは、急いで片手を壁に戻すと、「しーっ!」と、もう片手の人差し指をアンドレスの口元に立てた。
「大きな声を上げたら、敵兵に気付かれちゃいますってば」
そう言って、ニッと、あの茶目っ気たっぷりの笑顔を見せた。
月光に浮かび上がる、その明るい笑顔は、一瞬、ここが敵の要塞砲の真下であることを忘れさせる。
このジェロニモは、いかなる緊張場面にあっても、いつも自然に心和ませてくれるから不思議だ。
今やアンドレスにとって、彼は大切な配下の兵であると同時に、多分、それ以上に、親しい友のような存在に思えるのだった。
「ジェロニモ、君たち黒人兵たちは、みんな、すごく登り方が上手いなあ!」
素直に感嘆を滲ませて言うアンドレスに、ジェロニモは、スッと相手の上腕に触れて、ちょっと神妙な顔をした。
「あちゃあ、もう、こんなに腕が張ってる!
これじゃ、上までもちませんヨ。
多分、途中で落下。
海に向かって真っ逆さまってとこです」
「え…っ!」
「少し腕を休めてやらないと。
いいから、そっちの手でしっかり壁を掴んで。
それから、こっちの手は壁を離して。
そうです、で、その手を下に降ろして!
そして、こんなふうに軽く振ってみてください、俺みたいに」
ジェロニモはテキパキ指示をしながら、アンドレスに見えやすい方の自分の腕を降ろして、それを小刻みに揺らしてみせる。
なんとなくつられて、アンドレスも降ろした腕を同じように揺らしてみた。
すると、確かに、すうっと、腕の疲れが溶け去っていくような気がするのだった。

「少しは楽になりましたか?」
「ああ、ありがとう!
ジェロニモ、他の兵たちにも、教えてやってくれないか?」
「それはもちろんです。
あと、さっきの俺の両手離し、見てもらえました?
あの通り、足だけでも、かなり体を支えられるんです。
っていうか、手に頼るよりも、足で体を支えて、足の力で登っていく方が遥かに楽なんですヨ。
なんたって、普段から飛んだり跳ねたりしている足の方が、手よりもずっと持久力も筋力もあるんですから。
あとはスピードです!
こんな真垂直の壁は、傾斜のきつさは最大だ。
持久力をがんがん奪っちまう。
タラタラ登ってると、かえって疲れが増しちまって、上に着く前に消耗し尽くしちまいますヨ!」
身分的には雲上とも言えるほど上官のアンドレスに、いつも歯に衣着せずにズバズバ語るジェロニモに、周囲のインカ兵が聞き咎めて厳しく注意を促すことは、これまで度々あった。
しかし、当のアンドレス自身は、そんなジェロニモに嫌な感じを受けたことは殆ど無かった。
多分、それは、その態度や言葉遣いとは裏腹に、ジェロニモの眼差しに深い真摯さと誠実さがいつも溢れていたからだろう。
そして、多分、人種の違いを超えて、二人の感性は、どこか似てもいるのだ。
例えば、同じ一人の女性を愛しているという、二人だけしか知らない秘密――今では恋敵ということを超えて、かえって二人の絆を強める要素になっているようにさえ思える。

かつてジェロニモは、自ら身を引いて、アンドレスと彼女の仲をとりもってさえくれたのだった。
熱いものが込み上げ、アンドレスの片手は、首から提げているグランデーロのお守りに、胸甲の上からそっと触れていた。
(コイユール――!)
それから、笑顔で力強く頷いた。
「ジェロニモ、ありがとう!
できれば、俺に教えてくれたことを、俺みたいに四苦八苦している兵たちに、伝えてくれないか?」
耳打ちしたアンドレスに、ジェロニモは「もちろんです」と軽くウィンクを返すと、素早い身のこなしで別のインカ兵たちの方へ消えていく。
その姿を見届け、アンドレス自身も、「よし!」と、小声ながら気合を入れ直した。
そして、足元の感触を確かめ、ぐっと爪先に力を込めた。
その時、風に乗って、砦の高みから、アレッチェが皮相感たっぷりに何か言い放つ声が、不意に流れ聞こえてきた。
はっとして耳を澄ませば、トゥパク・アマルや「アンドレス」に扮したロレンソを屈辱的な言葉で誹謗する言葉が、途切れ途切れながらも、生々しく聞き取れた。
『そこの臆病者集団を率いている者、アンドレスよ、聞け!!
我々から盗み取った大砲を恥ずかしげも無く並べ立て、猿真似の弾撃ちを見せられるだけでも、見苦しきこと、この上無い!
その上、そのような屁っぴり腰で、しかも、そのような遠方に引っ込みながらの砲撃とは、及び腰にもほどがあろう!
これまで幾多の戦場で、インカ軍の見るに堪えぬ砲撃を目の当たりにしてきたが、おまえたちのような呆れた砲撃は、その中でも最低だ!!』
アレッチェの傲慢なせせら笑いまでもが目に浮かぶようで、アンドレスは、思わず掴んでいた石壁にギリッと爪を立てていた。
『だが、おまえたちよりも、もっと臆病なのはトゥパク・アマルだ!!
おまえたちのような軟弱な雑魚どもを最前線に押し出して、この期に及んでも、未だ遠く背後に引っ込んだまま、コソコソと身を隠していようとは!!』
それに引き続いて流れ来る、やんやと囃し立てるスペイン兵たちの揶揄まじりの喧騒。
(あいつら、トゥパク・アマル様に、なんてこと言いやがる!!)
挑発だと分かっていながらも、瞬間、アンドレスの全身が、ザッ、と憤怒で総毛立った。
周囲で石壁を登っている兵たちも、激昂に肩をいからせ、殺気立った目をこちらに向けてくる。
「アンドレス様、あの者ども……!!」
アンドレスは懸命に己の感情を抑えて、ゆっくり首を振った。
そして、小声ながらも、鋭く言い放つ。
「聞き捨てならぬ言葉だが、今は聞き流そう!
あれはスペイン側の挑発だ。
きっと、ロレンソたちは、今も砦の射程外で踏ん張っているんだ。
トゥパク・アマル様も、姿を現してはいないからこそ、アレッチェは挑発して誘い出そうとしている。
ならば、作戦は今のところ計画通りに進んでいるということだ。
それに、トゥパク・アマル様も、ロレンソたちも、あんな俗な手には乗りはすまい!
それよりも、一刻もはやくここを登りきって、砦に潜入すること――それが、俺たちにとって、今、何よりも優先すべきことだ!
さあ、急ごう!!」
アンドレスは石壁に向き直ると、先刻のジェロニモの教えを思い出しながら、手足を動かすピッチを速めた。
断崖下で逆巻く潮騒や波濤の砕ける音は、先ほどよりも遠くなってきている。
(確実に石壁を上がってきていることの証しだ。
もう半分以上は登ってきているはずだ。
このまま、ロレンソが上手くあいつらの注意を引きつけてくれていれば、俺たちが屋上階に乗り込むのも夢じゃない。
ロレンソ、踏ん張っていてくれよ――!!)

砦の石壁を這い上がりながら呼びかけるアンドレスの声に呼応するかのように、砦の反対側でアレッチェと対峙するロレンソの心も、アンドレスに呼びかけていた。
(アンドレス、我らのことは案ずるな!
それよりも、気を付けて登れよ。
屋上階の海側砲台にも、英国艦隊の再来に備えるスペイン兵たちが、まだ多数配備されているはずだ!)
今しがたまで砦のスペイン兵たちの間から湧き上がっていた下卑た野次や罵声も、再び強い苛立ちを含んだ沈黙へと変わっている。
それらの敵兵たちの中央に立つアレッチェの険しい表情が、未だ要塞砲の射程外に踏み止まるロレンソの方向を冷厳に見下ろしながら、傍に控えるサルセード大佐に低く言う。
「あの女を牢から連れてこい」
「承知いたしました、閣下!」
アレッチェの命に従うために、サルセードが数名の部下を引き連れ、ドタドタと石床を踏み鳴らしながら慌ただしく階下へ去っていく。
その間にも、軋みを上げそうなほどにビリビリ張り詰めた空気の中、睨み合うロレンソ軍とアレッチェ軍。
アレッチェは、眼下で陣頭に立つ『アンドレス』を、改めて、上から下まで、まじまじと凝視した。
その若者は、今も、自軍の兵が暴走することのないよう、険しく眼光を利かせながらも、あくまで平静を装った声で何かを言い聞かせ、逸る兵たちの心を鎮めんと努めている。
これまでの『アンドレス』の行動パターンに比して妙に沈着な行動傾向にしろ、闇の中とはいえ混血児にしては濃すぎる肌の色や髪色にしろ、どうにも腑に落ちぬ思いが募っていく。
アレッチェの苛ついた指先が、ガシッガシッと、己の顎を擦った。
そうしている間にも、サルセードたち一行が、騒然たる様相で、何者かを連れて屋上階に戻ってきた。

「ええい!!
歩く時ぐらい、大人しくしておることができんのか!!
インカ族の女は、みんな、おまえのように野蛮なのか?!」
サルセードの憤怒と困惑の混ざり合った声が響き、それを凌駕する勢いで、毅然と言い放つ女性の声が反響する。
「野蛮なのは、どっちよ!!
ちょっと、そんなに乱暴に引っ張らないでって言ってるでしょ!
そんなにグイグイやらなくたって、自分でちゃんと歩くわよ!
腕が千切れたら、どうしてくれるのさ?!」
己を引っ立てて歩くスペイン兵たちに抗議しているらしき女性の声は、男性陣の声よりもワントーン高く、広い空間に凛と響き、かなり距離がありながらも、ロレンソたちのいる場所まで鮮明に聞こえてきた。
(まさか…あの声は…?!)
あまりに聞き覚えのある声に、ロレンソは驚愕して耳を疑った。
心臓の凍る思いで、声の響いた方向に目を凝らす。
それから、愕然と目を剥いた。
「――マルセラ殿……!!」
我知らず悲鳴に近い声を発してしまったロレンソの背後で、彼の配下の兵たちもギョッと目を見開いて、砦を凝視したまま身動きできなくなっている。

まさしく、砦の手すり際に姿を浮かび上がらせていたのは、殊にロレンソにとっては、どれほど離れていようが見誤りようもない、マルセラ、その人だった。
カモシカのようにスラリと伸びた肢体に女性用の戦闘衣を凛々しく纏い、スッキリと短くカットした黒髪を真紅のバンダナで纏め上げている。
その姿は、昨日、英国艦隊とスペイン艦隊の戦況を偵察し、報告するために、沖合いの小島に渡っていった時のものと同じであった。
だが、今は、しなやかな若枝のような褐色の腕を後手に縛られたまま、アレッチェの前に、激しく抵抗しながら引き出されてきていたのだ。
このような形で敵中に囚われて、遠目からも口惜しそうな様子は窺えたが、それでも、少年のような風貌を毅然とさせて、あくまで気丈に振る舞っている。
そんなマルセラの様子が、かえって痛々しく、ロレンソは、目の前が真っ暗になる思いで立ち尽くしていた。
(まさか、昨日、偵察に出たまま、戻っていなかったのか?!
確か、英国艦隊とスペイン艦隊の戦況を探るために、沖合の小島に渡っていたはずだが。
も…しや、その時、スペイン軍の巡視艇か何かに見つかって、捕えられた…?)
思わず手の平から取り零しそうになった剣を、おぼつかぬ指で辛うじて握りとめる。
(なんと迂闊だったのだ…!
そなたが戻っていないことに、気付かなかったなんて……!)
とはいえ、実際のところは、アンドレスも、ロレンソ自身も、昨日のうちに本陣を出立しており、マルセラの所在を確認しようもなかったのだ。
また、恐らく、トゥパク・アマルをはじめ本陣に残っていた者たちも、英国艦隊の襲来やミカエラたちのサンガララ戦に意識を奪われ、怒涛のように過ぎる時間の中、マルセラが戻っていないことに気付くいとまも無かったのであろう。
いや、そもそも、元気闊達で、物怖じせず、それでいて、叔父ビルカパサ似の冷静さや才気もそれなりに持ち合わせている彼女は、放っておいても、大概のことは自身で何とでも乗り切れる――そのような空気が、インカ軍幹部の間に定着していたのだ。
ロレンソは、完全に血の気の引いた顔を、震える左手で拭った。
(ああ…誰よりも、わたしが、もっと、心を配っていれば……!)
そのようなロレンソの苦悩を見透かすかのように、砦の屋上階では、マルセラの肩を背後から掴んで、彼女の体を手すりに押し付けながら、アレッチェがあの嗜虐的な笑みを浮かべている。
「さあ、この女がここから突き落とされる前に、早く助けに来てやったらどうだ」

一方、マルセラは、己の背を強引に押して手すりから身を乗り出させていくアレッチェの腕力に抵抗しながらも、眼下の大軍に目をやってハッと息を呑んだ。
(あれは、アンドレス様の軍…?!
ううん、違うわ――ロレンソ殿!!)
今も砦の射程圏外に踏みとどまる若きインカ兵たちの陣頭に立ち、遠目からもありありと分かるほどに、真っ青な表情をして、こちらを見上げている将兵の姿。
アンドレスの戦時の身なりをしてはいるが、そこにいるのは、マルセラにとっても、見誤りようのない特別な人物だった。
マルセラは、黒曜石のような瞳を大きく見開いていく。
そして、開戦前に、トゥパク・アマルや側近たちと話し合った作戦を即座に思い出した。
(そうだわ!
作戦上、ここでは、ロレンソ殿が、アンドレス様に扮することになっていたんだっけ!)
マルセラの瞳が、激しく揺れはじめる。
(ロレンソ殿…!)
いつだったか、ロレンソと交わした言葉が、不意に、マルセラの耳奥に甦ってきた。
『いけません。
そなたは戦線に出てはなりません』
『ロレンソ殿!!
私に指図をするおつもりですか?!』
ロレンソは深く息をつき、その大人びた表情に優しい光を宿してマルセラを見つめた。
『そなたは女性なのです。
もっと御身を大切になさい』
『なっ…何を、いきなり言うのです…!!』
応戦しようにも、すっかりドギマギして言葉の出ないマルセラに、ロレンソも静かにはにかんだ。
そして、慈しみを込めた眼差しで見下ろし、そっと囁いた。
『――そなたには、死んでほしくないから』
今、眼下で、背後に多数の部下たちを従えていることさえ忘れてしまったかのような愕然たる表情で、呆然とこちらを見上げているロレンソの姿に、マルセラの胸は締め付けられる。
彼女の懐には、かつてロレンソから贈られたインカローズの石が、今も大切に仕舞われていた。
(ロレンソ殿……!)
このような事態を招いて、ひどく情けない思いと、あまりの申し訳なさと、そして、このような状況にもかかわらず、ロレンソの姿を見た安堵感からなのか、愛おしさからなのか――気丈に張り詰めていた力が、一気に抜け去っていきそうだった。
マルセラは強く唇を噛み締めて、込み上げそうになった涙を振り払った。
その間にも、アレッチェの腕が、荒々しく掴み上げたマルセラの肩をさらに押して、ますます彼女の身体を手すりから大きく乗り出させていく。
女性としては長身で、いっぱしの女戦士の身なりなど装っているとはいえ、厳めしい軍人の体格をしたアレッチェの前では、マルセラとて、華奢な一人の少女にしか見えない。
そのアレッチェの手に掴み上げられて、体半分以上を手すりの外へ押し出される格好になっているマルセラの足は、恐らく、もはや石床にはついていないのではないかと思われた。
ロレンソ軍の兵たちの間から、悲鳴混じりのどよめきが湧き上がる。
ロレンソの喉からも、声にならぬ叫びが漏れた。
これまでも、非戦闘員であるインカ族の平民たちまで駆り出してきて、それらの民衆を平然と人柱としてスペイン軍の前面に括りつけ、生ける盾とまでしてきたアレッチェの仕儀。
あるいは、トゥパク・アマルの攻撃の矛先を鈍らせるために、同じインカ族の数万の傭兵集団を養成し、同族同士の大規模な流血を強要したこともあった。
目的達成のためなら手段を選ばぬ容赦無さ、冷酷さを、散々に見せつけられてきただけに、捕虜となったインカ族の女の一人や二人、突き落とすことなど、このアレッチェなら朝飯前だろう。
そう予測できるが故に、ロレンソはもとより、ロレンソ軍の誰もが顔面蒼白になったまま、その場に凍りついている。
「さあ、どうするのだ?
もっと傍まで来て、我らと堂々と戦って、この女を奪い返すのか?
それとも、そこに引っ込んだまま、見殺しにするか?」
そうアレッチェが言い終わるよりも早く、マルセラの決然とした声が、夜空に高く響き渡った。
「『アンドレス様』!!
こんな安っぽい挑発に乗っては、だめ!!
絶対に来てはいけません!!」

その頃、砦の海側方面の石壁を無我夢中で登っていたアンドレスたちの一団にも、屋上階での喧騒が、風に乗って届いてきていた。
夜の大気を震わせて凛と響き渡る聞き慣れた女性の声、そして、断片的ながらも聞こえくるアレッチェの言葉――それらを耳にして、アンドレスもまた、愕然とその場に凝固した。
(まさか、マルセラ?!
なんで、こんなところに?!)
アンドレスの周囲のインカ兵や黒人兵たちも、衝撃を隠せぬ表情でアンドレスの方を振り向き、声無き声で叫んでいる。
「あれは、マルセラ様の声では?!
もしや、砦のスペイン軍に囚われているのでしょうか?!」
アンドレスも、衝撃を隠しきれぬ表情で、呆然と頷いた。
何とかして起こっている事態を把握しようと、必死で耳をそばだてながら、頭を整理しようとする。
(きっと、昨日、マルセラが、敵軍同士の海戦の偵察に出た時だ。
あの時、スペイン兵に見つかり、補縛されたに違いない…!)
アンドレスは、自身の手足が震えてくるのを感じた。
(敵の目につきにくいようにと、ほんの数名で偵察に乗り込んでいったが、それがまずかったか!
それもこれも、俺やトゥパク・アマル様の計画の甘さだ……。
マルセラ、すまない――こんな目に合わせて…!)
常に、強気に、気丈に振る舞うマルセラの、実は、気弱で繊細な一面も、幼い頃から彼女と付き合いの長いアンドレスは、良く知っていた。
それに、こんな状態のマルセラを目の前にして、ロレンソはどんな思いでいることだろう?!
もし自分の愛するひとが、同じ境遇におかれたら――!
アンドレスの背を、幾筋もの冷たい汗が伝い落ちる。
(まずい…まずい事態だぞ…。
ロレンソ、先走っちゃ駄目だ!!
マルセラは、すぐに俺が助けに行くから、堪えてくれ!)
アンドレスは、険しい表情で周囲の兵たちを振り向いた。
「急ごう!!
一刻も早く、ここを登りきらねば!」
このような場所で兵たちの不安をこれ以上煽らぬよう、懸命に己の動揺を押し隠しながら、アンドレスが皆を鼓舞する。
とはいえ、振り仰ぐ遥かな屋上部までは、まだ3分の1以上の長い距離が残されている。
「くそぅ…!」
固い石壁に拳を叩きつけるアンドレスの胸甲の下では、今にも張り裂けそうなほどに、激しく心臓が脈打っていた。
さらに、同じ頃、出撃の時を計りながら樹林地帯に潜んでいたトゥパク・アマルたちインカ軍本隊もまた、衝撃の空気に包まれ、騒然となっていた。
背後に大軍を控えさせて陣頭に立つ騎馬のトゥパク・アマルも、その横顔に強く案ずる面差しを宿し、険しくなった切れ長の目の端が微動している。
彼の唇から、悔恨の声が漏れた。
「昨日の海戦、現場を偵察するマルセラ殿の報告の秀逸さ、詳細さに目を奪われ、まさか当人が戻っていないことに気付かぬとは、なんと迂闊だったことか…!」
己自身を激しく悔いながら、マルセラの叔父でもあるビルカパサの方へ、苦しげな視線を向けた。
「そなたの大切な姪子殿が、このようなことになり、詫びの言葉も無い」

対するビルカパサは、唇を噛み締めて首を振り、その厳つい体躯を深く低めた。
「トゥパク・アマル様、めっそうもございません。
インカ軍にとって、このような重要な局面で、マルセラがあのような不始末を仕出かし、もはや償いのしようもございませぬ。
すぐにも、この命で購(あがな)いたい思いでございます。
皆々方にも、申し開きの言葉も無く――」
彼の言葉をそのまま裏付けるかのように重い苦悩に覆われゆくビルカパサの表情は、同時に、姪を心から案ずる叔父のそれでもある。
「何を申すか!
英国艦隊や迎撃するスペイン砦の動きに即応できたのは、危険を顧みずに現地に飛び込んだマルセラ殿が、微に入り細に渡った報告をわたしに届け続けてくれたおかげなのだ。
しかし、そのような危険な地に、少人数しか送り込まなかった我が身の判断の誤りこそ、口惜しくてならぬ」
胸詰まる思いでそう応えるトゥパク・アマルの周りで、他のインカ兵たちも、「ビルカパサ様、どうか顔を上げてください」と、口々に言う。
そんな兵たちの姿をひとしきり見渡してから、トゥパク・アマルは、今一度、砦の最上階へ視線を戻した。
「いずれにしても、こうなっては、このままというわけにはいかぬな。
即刻、手を打たねばならぬ」
意を決した声音で言ったトゥパク・アマルに、ビルカパサも、「はっ…」と、恭順を示した。
「わたしも同じ考えでございます。
と、申しますのも――」
そう言いさして、僅かに言葉を呑み、それからビルカパサが語を継いだ。
「私的なことではございますが、実は、ロレンソ殿とマルセラは、恋仲にありまして」

思いがけぬビルカパサの発言に、トゥパク・アマルの瞳が大きく見開いていく。
「なんと、そうであったのか」
まだ身を低めつつも僅かに顔を上げたビルカパサの瞳が、トゥパク・アマルを真剣な眼差しで見つめる。
「はい、トゥパク・アマル様。
ロレンソ殿をアンドレス様と思い込んでいるアレッチェが、あの二人の仲まで知っていたはずはありますまいが、偶然とはいえ、このような事態ともなると、ロレンソ殿のことが強く案じられます」
トゥパク・アマルも、俊敏に頷いた。
「ロレンソ殿とマルセラ殿が、そのような仲となっていたことは、わたしとしても、大いに喜ばしいことだ。
だが、そうであるとすると、そなたの言う通り、ロレンソ殿のことが心配だ。
いかに冷静な彼とて、この状況にあっては、その心情は平静ではいられまい」
「はっ、トゥパク・アマル様。
万一、ここでロレンソ殿が踏み外すようなことがあれば、彼の軍も多大な危険に晒されることになりましょう。
果ては、我らインカ軍の作戦全体も、総崩れになりかねません。
なれば、直ちに、我が兵を率いて、ロレンソ殿の援護に馳せ参じたく!」
そのビルカパサの進言に、トゥパク・アマルは、「いや」と、素早く首を振った。
「我が軍全体やロレンソ殿を思うそなたの忠義は良く分かる。
しかし、ここは、わたしが参る。
どの道、わたしが出て行かぬことには、アレッチェ殿はおさまらぬ」

「なんですって?
トゥパク・アマル様ご自身が、アレッチェの前面に出て行くと仰るのですか?!
そのようなことはなりませぬ!!」
「ビルカパサ、今は、揉めている時の猶予は無い。
騎兵部隊の一部を借りるぞ」
「お待ちください!!
トゥパク・アマル様、それは、あまりに危険です!
アレッチェの全ての言動は、陛下を砦の正面に引き摺り出すためのものなのです。
ここで陛下自身が出ていかれては、あの者の思う壺となってしまいます!」
「ビルカパサ様の仰るとおりです!
陛下、お待ちください!!」
必死にトゥパク・アマルを思い留めさせようとするビルカパサと呼応するようにして、他のインカ兵たちも、トゥパク・アマルを懸命に止めようとする。
それらを敏捷な身ごなしで騎馬のまますり抜け、トゥパク・アマルが、愛馬の手綱を手繰り寄せた。
「わたしが出ていかねば、かえって、全員の危険が増すのだ。
――それに、わたし自身が出ていけば、アレッチェ殿は、きっと、砦の外に潜めているであろう彼の伏兵部隊を動かすに違いない。
我らにとっても、あの者の伏兵たちを表に引き摺り出すことができれば、むしろ好都合ではないか。
その時には、ビルカパサ、そなたが指揮して、我らの本隊を動かしてくれ」
そう厳然と、且つ、口早に言い放つと、鋭い掛け声と共に砦に向かって白馬を駆り出していく。

そのトゥパク・アマルの瞬時の動きに遅れを取るまじと、騎馬部隊800騎が、砂埃を蹴立てながら、主の後を追って勢い良く飛び出していった。
その頃、砦の屋上階では、アレッチェの手で荒々しく肩を掴み上げられ、体の半分以上を手すりから宙に乗り出させられた格好のマルセラが、精一杯に考えを巡らせていた。
(作戦では、今頃、アンドレス様の軍が、この砦の海側の壁を登っているはずだわ。
ああしてロレンソ殿がアンドレス様を装っているのも、ここにいるアレッチェたちの注意を引きつけて、アンドレス様たちが砦に乗り込んでくる時間を稼ぐため。
ならば、私も、一刻でも時間を稼がなきゃ…!)
唇を噛み締め、気合いを入れ直すかのようにして、後手に縛られた腕にぐっと力を込めた。
(トゥパク・アマル様も、叔父様も、きっと見てるわね…こんな情けない姿……!
だけど、私だって、こんなところで、こんな奴に、本当に突き落とされるわけにはいかない!)
とはいえ、己の全身は今もアレッチェの強靭な指で易々と持ち上げられ、手すりの向うに大きく押し出されている。
アレッチェが己の肩を掴み上げている手をひとたび離せば、衆目の面前で、30メートル以上も下方の地上に、真っ逆さまに転落することだろう。
アレッチェにしてみれば、捕虜を、一人、処刑するにすぎず、この男ならそれくらいのこと、何の抵抗も無くやってのけるに違いない。
それが分かるだけに、マルセラの本心は、身の凍る思いであった。

それでも、彼女は意を決すると、背後に立つアレッチェの方へ、キッ、と首を回した。
「言っておくけど、この私を、突き落としたりしない方がいいわよ!」
時間稼ぎのために切り出した言葉であったが、己の内面の怯えが声に滲んではいまいかと、マルセラは密かに固唾を呑んだ。
アレッチェが、苛立たしげに片眉を吊り上げて、半顔ほど振り向いているマルセラの横顔を睥睨する。
「この期に及んで命乞いか?
残念ながら、おまえをここから突き落とすか否かを決めるのは、わたしではない」
そう言って、アレッチェは、砦の向うに布陣するロレンソたちの方を顎でしゃくった。
「あそこにいるインカ軍の若造どもの動き次第だ。
あの者どもが、我らの要塞砲を恐れず、おまえを助けに来る心意気を見せるならば、突き落とすのを暫し待ってやる。
だが、おまえが、あの者どもにも見放されるようなら、わたしも、おまえには用済みだ」
「あそこにいる『アンドレス様』たちの軍は、決して、あそこから動かないわ!
トゥパク・アマル様への忠誠心は、とても固いの。
ご命令に背いて、勝手に兵を動かすようなことは、『アンドレス様』は、決してならさないわ。
だから、こんなことをしても無駄よ!」
不意に、アレッチェの腕が、グイと、マルセラの体をさらに大きく手すりから押し出した。
「それ以上、余計な無駄口を叩くと、今すぐに――」
憎悪に満ちたアレッチェの両眼が氷のように冷たく光るさまに、マルセラは、心の底で震え上がりながらも、表向きは気丈な表情を懸命に保ったまま、アレッチェの言葉を遮った。
「ち、ちょっと待って!
私の言いたいことは、これからよ!」

いよいよ苛立ちを強めるアレッチェの険しい形相の前で、まるで蛇に睨みつけられた蛙のように、心臓も、舌も凍りついて、言葉の呂律が回らなくなりそうな己を、もう一人のマルセラが『しっかり!!』と叱咤する。
マルセラは、懐に忍ばせたインカローズの石に、縋るような思いで意識を向けた。
生きて脈動しているかのような石の霊妙な波動を感じた瞬間、かつてのロレンソの言葉が、温かく、力強く、心の中に響き渡った。
『マルセラ殿、これは"インカの真珠"――インカの黄金時代から、特別な力があるとされてきた石。
この石は、我々の意識を、宇宙や大地の力と結び合わせ、さらに高みへと導いてくれる力があると古くから言い伝えられています。
これは、わたしが戦さの時、常に身につけてきたもの。
それを、今度は、そなたに持っていてほしいのだ。
必ずや、そなたを守護してくれましょう』
(――ロレンソ殿……!)
マルセラは、深く息を吸い込むと、今一度、キッと、アレッチェを鋭く見返した。
「さっき、牢の中であなたの部下に尋問された時は、適当に誤魔化したけど、私は、トゥパク・アマル様の腹心ビルカパサの姪のマルセラよ!」
その言葉に、アレッチェの片眉が、再びピクリと上がった。
「あのビルカパサの姪?
おまえがか?」
アレッチェが微かに関心を示した気配を敏感に察知しながら、マルセラが、さらに言葉を継いでいく。
「そう、あのビルカパサの姪よ。
だったら、こんなところで突き落としてしまうより、もっと有効な利用方法があると思わない?
例えば、人質にして、もっと重要な交渉ごとのために、取っておいても損はないでしょ?」
自分でそうは言いながらも、本当にアレッチェが、そのような手に出たらどうしようと、マルセラの心臓はバクバクと身から飛び出しそうに脈打っている。
しかし、一刻でも時間を稼ぐためなのだ――彼女は、必死でポーカーフェイスを装いながら、横顔で微笑んでみせた。
一方、アレッチェも、冷やかに口端を吊り上げて、苦笑交じりに言う。
「なるほど、おまえがマルセラか。
かのクスコ戦の前、トゥパク・アマルの使者として、モスコーソ司祭の前に一人でのこのこ出向いていった命知らずな小娘がいたと聞いたが、それは、おまえか。
これは、面白い魚が網にかかったものだ」
アレッチェの黒眼が弾丸のような冷酷な光を強めるさまに、マルセラは、ついに堪えられなくなって顔を強張らせた。

突如、己の肩を掴んでいた肩から、フッと、アレッチェの鋼のような指が離れた。
「――!!」
ズッ、と引力に引き摺りこまれるように落下しかけたマルセラの肩を、またアレッチェの手が荒っぽく掴み止める。
頭から落ちかけた身を上から乱暴に掴まれて、マルセラの若枝のような肢体は、ガクンッ、と弓のように反り返った。
手すり際に引っ張り上げられたものの、一瞬、本当に落ちかけた衝撃と恐怖に、マルセラは、己の全身から、ザアッ、と血の気が引いていくのを感じていた。
止めようにも、体中が、ガクガク激しく震え出す。
その様子を酷薄な面持ちで冷徹に睥睨しつつ、アレッチェの腕が、今度は己自身の方に向かせてマルセラを立たせ、彼女の背を手すりに強く押し付けた。
そうしながら、冷厳な声を凄ませ、矢継ぎ早に詰問する。
「あのビルカパサの身内ともなれば、知っていることも多かろう。
さて、おまえたちの企みを全て吐き出してもらおうか。
トゥパク・アマルは、今、どこにいて、何をしようとしている?
あそこに布陣している若造どもを率いているのは、本当に、アンドレスか?
あるいは、あそこに替え玉を置いて、我々の注意をあの者どもに引き付けている間に、何か良からぬ策を講じようとしているのではあるまいな?」
「し、知らないわ!!
詳しい作戦の内容までは、私みたいな下っ端の側近には…!
それに、あそこにいるのは、間違いなく『アンドレス様』たちの軍よ!」
「インディオ女め!
ふざけるな!!」
次の瞬間、アレッチェの猛烈な平手打ちがマルセラの頬に飛んだ。
その衝撃に、手すりの向こうへ吹っ飛びそうになったマルセラの体を引っ掴んで、アレッチェの強打が彼女のもう片頬に叩きつけられる。
「女だと思って手加減していれば、図に乗りおって。
このわたしを、誰だと思っている」
遠目からも見るに堪えぬその光景に、ロレンソの堪忍袋の緒は、ついに、ぶち切れた。

炎のような双瞼で砦の頂上を睨み上げながら、怒りに震える指で剣の柄を捻り潰すほど強く握り締めている。
己の気を鎮めるために敢えて鞘に収めていた剣であったが、今再び、彼の手は、ズズッと、重厚な刀身を引き抜いていく。
「これ以上は、傍観に堪えぬ……!」
低く呻いたロレンソの周りでは、同様に憤りで顔を赤黒く染めたインカ兵たちが、「ロレンソ様、出撃のご命令を!!」と口々に猛々しい声を上げている。
ロレンソは、刀身を中空で一閃させると、ビッ、とアレッチェの方角を剣先で鋭く突いた。
「これより、砦に向けて進撃を開始する!
歩兵機動部隊は、突撃準備隊形にて待機。
まず、砲列部隊第一戦列が、砦への砲撃を開始せよ。
その間に、砲列部隊第二戦列が砦に向かって、速やかに前進。
砦を射程内に収める位置まで前進したら、一旦停止し、その場で第二戦列が砦への砲撃を開始。
その隙に、第一戦列が、さらに深く前進し、砲撃を再開。
続いて、第二戦列が、さらなる至近距離まで砦に肉薄して砲撃を再開。
砦を十分な射程内に収めたら、第一戦列、第二戦列とも、各地点から制圧砲撃を続行。
その間に、歩兵機動部隊が一斉前進せよ。
砲列部隊両戦列の援護のもと、歩兵機動部隊は砦の真下まで突撃し、そのまま正門を打ち破って、砦内部への侵入を図る!」

己の言葉に耳をそばだてながら、眼光炯々として腕を鳴らしている兵たちに、ロレンソも力強く頷き返した。
「これまで幾度も訓練を積んできた戦法だ。
そなたたちなら、必ずや成し遂げられよう!
行くぞ!!」
「オー!!」
若き兵たちの雄々しい鬨の声が、天に高々と響き渡っていく。
他方、砦の屋上階では、その声に聴き耳を立てながら、アレッチェが冷笑を浮かべていた。
「単細胞な愚か者たちよ。
どうやら動く気になってくれたようだな」
それから、アレッチェは、サルセード大佐に目をやって、手すりぎわにズラリと並んだ要塞砲の群れを顎でしゃくった。
「あの青二才のインカ兵どもが十分な射程圏内に入るまでよく引き付け、その上で、我らの要塞砲の威力をたっぷり味わわせてやるがよい。
このアンドレス軍とやらの歩兵と砲兵を早々に潰しておけば、後に現れようトゥパク・アマルのインカ軍主力部隊を叩く上でも有益だ」
「はっ、閣下!
まこと、仰せのとおりかと。
それにしても、さすがはアレッチェ様ですな。
何の役にも立ちそうにないと思われた捕虜の小娘を使って、あの頑固に動かぬ敵兵を我らの思う壺にはめるとは」
そう言って下卑たしたり顔を向けた視線の先では、アレッチェの猛打によって石床に打ち倒されたままのマルセラが、血だらけの顔に堪えきれぬ涙を浮かべながら、懸命に身を起そうとしている。
対するアレッチェは、「いらぬお喋りは謹んでもらおうか、大佐」と、冷たくサルセードを一蹴した。

「それより、砲弾を詰め込んだ釜に、大火を焚いておくのを忘れるな。
英国艦隊に見舞う予定だった赤熱弾を、代わりに、奴らを逃がしてやったインカ兵どもに引き受けてもらおうではないか」
そのアレッチェの言葉に、サルセードがハッとして、たぷついた頬を躊躇いがちに揺らした。
「ですが、アレッチェ様。
あそこのインカ軍に向かって赤熱弾を大量に放てば、この砦の麓に広がる荒れ野に火災を引き起こす恐れがあります。
そうなれば、こちらにまで火の手が回ってくる危険がありましょう」
「そのことなら、案ずることはない」
そう言って、アレッチェは、上空の方をサッと一瞥した。
先程まで星が瞬きスッキリ晴れ渡っていた天頂に、今は薄雲がかかりはじめている。
遥か遠くでは厚い雲が立ち込め、雷鳴がゴロゴロと低く轟いているのが聞こえてくる。

空を見上げているサルセードに視線を戻し、アレッチェが再び口を開いた。
「やがて、ここにも雨がやってこよう。
しかも、あの様子では、かなり強く降りそうだ。
多少の火の燃え広がりは、豪雨がなんとでもしてくれる。
それより、我らとしては、天候が崩れる前に、インカ軍を始末してしまうことが肝要だ。
焼け爛れた砲弾を浴びた兵たちの惨状を目の当たりにさせれば、インカ軍全体の恐怖心や混乱を煽り、士気を貶め、よい見せしめにもなろう」
「ごもっともです、閣下」
サルセードは大袈裟なほど首を上下させて頷き、砲主長の方に「準備をしろ!」と目配せしてから、さらに語を継いだ。
「あのこざかしい若い将兵にも、よく狙い定めて、ぶっぱなしてやりましょう」
その二人の言葉を愕然と聞いていたマルセラが、どこに力が残っていたのかと思われるほどの勢いで、ガバッ、と立ち上がった。
と見るや、自ら手すりぎわに走り寄り、眼下のロレンソ軍に向かって渾身の力で叫んだ。
「来てはだめ!!
熱弾を打ち込むつもりよ!!」
マルセラの決死の叫びが終るよりも早く、アレッチェの振り上げた頑強な軍靴が、彼女の柔らかな腹部に思い切り蹴り込まれた。
「――!!」
血を吐きながらむせるマルセラの体が、石床に激しく叩きつけられる。
強打のために意識朦朧となっているマルセラの襟首を、むずと掴んで引き摺り起したアレッチェの形相には、はち切れんばかりに青筋が立っている。
「下賤なインディオ女め。
それほど殺されたくば、願い通りにしてくれよう」
今にも手すりの向う側にマルセラの体を放り出さんとしているアレッチェの傍で、サルセードが、けたたましく叫んだ。
「あ!!
閣下、お待ちを!
あれは、トゥパク・アマルではありませんか?!」
「――!」
次の瞬間、アレッチェの手から、マルセラの細い体が、ドサリ、と床に転がり落ちる。
アレッチェの全神経は、完全に眼下へ吸い寄せられていたのだ。
彼の視線の先では、突如現れたインカ軍騎兵部隊が、砦の射程内に進軍しようとしているロレンソ軍の長大な戦列を、外周から包み込むようにして、蹄音高く駆け込んできていたのだった。

「全軍、進軍を止めよ!!
断じて、前に出てはならぬ!!」
そう厳然と号を発しながら疾駆する逞しい白馬――漆黒の長髪をなびかせ、手綱を巧みに繰るその黒衣の人物に、アレッチェの目は、いやがうえにも引き付けられる。
(トゥパク・アマル――!!)
トゥパク・アマルは、若武者たちの陣頭に立つロレンソの方へ、まっしぐらに馬を駆り立てていく。
その進路に布陣していたロレンソ軍の兵たちが、トゥパク・アマルのための通り道を次々と開いていく。
それらの兵たちに眼差しで礼を払いながら駆け抜けていくトゥパク・アマルの周囲では、「トゥパク・アマル様!!」「陛下!!」と、熱狂的な歓声が波のように広がっていく。
屋上階から見下ろすアレッチェの目には、広大な湖面が真っ二つに割れて、そこに整然たる道が現れていくかのような光景であった。
その道を一気に走り抜けたトゥパク・アマルが、ハッとこちらを振り向いているロレンソに、鋭く頷いて馬を寄せた。
「ロレンソ殿、待たれよ!!
前進は、ならぬ!」
「トゥパク・アマル様、申し訳ございません…!
ですが、わたしは――!」
平素の沈着なロレンソとは別人のように、殺気だって血走った目を向ける眼前の若き将兵を真直ぐ見つめたまま、トゥパク・アマルは俊敏に馬から飛び降りた。
その力強い手が、ロレンソの肩を、ガッシ、と包むように押える。
「ロレンソ殿」
「トゥパク・アマル様…!」
「ロレンソ殿、ここは堪えてくれ。
事情は、ビルカパサから聞いた。
そなたの気持ちは、良く分かる。
だが、あのような強壮な火力により防護された敵陣に正面突撃を仕掛けるのは、あまりに危険が大きい。
そなた自身も、そなたの隊の若き精兵たちも、尊い命を散らすことになろう。
そなたを失って、一番悲しむのは誰だと思う?」
「トゥパク・アマル様……!」

低く響く静かな声音で噛み締めるように語るトゥパク・アマルの前で、ロレンソの眼光は僅かずつながらも鎮まっていく。
そのようなロレンソの様子に、トゥパク・アマルは、再び深く頷き返した。
「マルセラ殿のことは、わたしとて身を切られる思いなのだ。
しかし、少なくとも、今ここで、彼女が即座に命を奪われることはないと考えてよかろう。
あの者の暴虐な振る舞いは見るに耐え難きものであるが、それでも、命まで奪うことはしないはず。
ビルカパサの身内でもあるマルセラ殿を、ここで易々と殺してしまうのは惜しいということを一番よく分かっているのは、他でもない、計算高いあの者自身なのだ。
それに、我らも、これから現れるに相違ない敵の伏兵と一戦交えたら、いずれにしろ砦の内部へ急行せねばならぬ。
アンドレスの率いる部隊は兵力500、対する砦のスペイン兵は、斥候の報告から1000以上と見積もられる。
アンドレスたちだけでは対処しきれまい。
それに――」
トゥパク・アマルは、その真摯な双瞼で、怜悧な光を取り戻したロレンソの瞳の奥深くを見据えた。
「マルセラ殿とて、アンドレスよりも、誰よりも、そなたを待っていることであろう」
「トゥパク・アマル様…!!」
様々な思いが込み上げ言葉にならぬロレンソの肩を、トゥパク・アマルの逞しい手が、今一度、しっかりと握り締めた。

「砦に進軍する前に、我らが対峙せねばならぬ敵勢も、そう少数では済むまい。
ロレンソ殿、覚悟は良いか?」
「トゥパク・アマル様、申し訳ございません。
このようなことになり、陛下をあのアレッチェの面前に来させてしまうなど――!」
「いや、むしろ、これで良いのだ。
わたしが出て来ぬうちは、アレッチェ殿は、砦外に敷いた伏兵を動かさぬ。
あの者が、あれほどの砦に1000の守備兵しか残していないのは、我らを砦の外で待ち伏せる大軍に多くのスペイン兵を回しているからに他ならない。
故に、その伏兵たちを討ち取らずには、いずれにしろ我らに勝機はないのだ」
そうロレンソに応じて、トゥパク・アマルは、ぐっと首を上げ、高い砦の屋上階を見やった。
そこには、案の定、眼光を炯々とさせたアレッチェがいて、こちらを微動だにせず見据えている。
トゥパク・アマルとアレッチェの視線が、宙を切り裂いて、ぶつかり合う。
距離を隔てながらも、互いに相手の存在を、手を伸ばせば掴みかかれるほどに直近に、生々しく感じ取っていた。

遠い夜空では稲妻が閃き、低く雷鳴が轟いている。
実際には僅か数秒の時間であったが、二人には数分にも思える長い時間、ギリギリと睨み合った後、互いに視線を引き剥がした。
「予定通り、砦の外に潜ませた部隊を動かせ」
感情を押し殺した冷徹な口調で命じたアレッチェに、「はっ」と恭順を示してから、サルセードが、むっちりした両手の指を擦り合わせた。
「閣下、この小娘は、いかがいたしましょう?」
「牢に戻しておけ。
トゥパク・アマルが自ら現れて来た以上、当面、その女に用は無い。
ビルカパサの類縁ならば、後々、いくらでも利用価値はあろう」
関心を失った冷たい声で命じたアレッチェの言葉に即応し、サルセードが、近くに控えていた巨体のスペイン兵に視線を投げた。
「この小娘を、牢に運んで行け」
「はっ!」
応えたスペイン兵の巨躯が、気を失って床に倒れ伏しているマルセラの方へ近づいていく。
グッタリして身動きしない彼女の体を、ぐっと、荒っぽく引き起こしかけて、その兵の太い腕がハッと止まった。
「娘が何か言っています!」

傍にいたサルセードが素早くそちらを覗き込んで、「まこと、小娘が何か言っておりますぞ、閣下!」と、興奮気味に鼻息を荒げた。
彼らの言葉通り、血に染まったマルセラの口元が、うわ言を囁くように微かに動いている。
当のマルセラ本人は、今しがた石床に頭ごと叩きつけられた衝撃で脳震盪を起しており、今も意識を失って昏睡状態のままである。
「アレッチェ様、ほら、また何か言っていますよ!」
マルセラの顔を深く覗き込んだサルセードの上方から、アレッチェも、そちらを見下ろした。
アレッチェやサルセードをはじめ、周囲のスペイン兵たちが注視する中、マルセラの血らだけの唇が震えながら、懸命に擦れ声で何かを訴え続けている。
「…ロレ……ソ…ど――。
――来…は…だ……」
その途切れ途切れの言葉を聞き取ろうと、サルセードが重たそうな頭を傾けながら、己の顎をザラザラと撫でた。
「何を言っとるのか、意味不明ですな。
いかがいたしましょう、閣下」
アレッチェも不審そうに眉を顰めていたが、「後で訊問する。それまで牢に繋いでおけ」と言い捨て、眼下のトゥパク・アマルたちへ視線を戻した。
今、この場で強引にでも意識を取り戻させて詰問すべきではという思いもよぎったが、恐らく、そこまですれば息絶える可能性が高いという予測もついた。

マルセラと共に捕えたインカ兵たちにも既に拷問を加えてトゥパク・アマルの作戦を厳しく追及していたが、皆、貝のように口が堅く、結果、牢内で半死状態になっていた。
(後々の利用価値など余計なことを考えなければ、この女とて、今ここで殺してでも吐かせるのだが)
憔悴したマルセラを易々と担いで階下に降りて行く巨兵の靴音を背後に聞きながら、ビルカパサの身内でさえなければ、というジレンマがアレッチェの中で燻ぶる。
それほどに、今のマルセラのうわ言めいた言葉が、アレッチェの心に妙に強く引っかかっていたのだった。
砦の屋上階でアレッチェらが聞き取れぬマルセラのうわ言に耳を欹(そばだ)てていた頃、麓のトゥパク・アマルたちもまた、敵の次なる動きに備えて慌ただしい動きを見せていた。
敵勢の来襲に備えるために新たな戦闘隊形へ移行させるべく、素早い身ごなしで再び馬上に戻ったトゥパク・アマルの元に、土埃を蹴立てながら伝令馬が駆け込んできた。
すかさず下馬しようとした兵を、「そのままでよい」と素早く制して、「それで敵の伏兵の数は分かったか?」と口早に問う。
「はっ!」と、兵は深く礼を払ってから、険しい顔を上げた。
「砦外に潜んでいた敵軍は、早くもこちらに進軍中であります!
その数、総勢約3000。
うち歩兵約2000、騎兵約1000。
全軍が歩騎兵混成の三個縦列に分かれ前進中であります!」
その報告に、トゥパク・アマルは頷き、鋭く目を細めた。
「報告、ご苦労であった。
引き続き、しかと敵の動きを監視してくれ」
「はっ!」
兵が力強く礼を払って、たちまち黒馬と共に夜の闇に吸い込まれていく。

敵軍を見通すかのように鋭利な輪郭を闇の向こうに振り向けながら、トゥパク・アマルが言う。
「ロレンソ殿、そなたの率いる歩兵部隊が、約700。
そして、わたしがここに率いる騎兵部隊が、約800。
その1500の兵力で、敵軍3000と対峙せねばならぬようだ」
「覚悟はできております。
ここにいる我が部隊の兵たちも、全員、同じ気持ちでありましょう!」
凛々しい眼差しできっぱり応えたロレンソに、トゥパク・アマルは瞳で微笑み、俊敏に頷き返した。
「心強く思うぞ、ロレンソ殿」
それから、トゥパク・アマルは、馬上からロレンソ軍全体を大きく見渡し、砦の敵兵に聞き取られぬようインカのケチュア語で厳然と声を張った。
「皆の者よ、よく聞いてくれ!!
敵の大軍3000が迫っている。
それらの大軍と砦の間に我らを挟み込み、砦の射程内に追い込んで我らを要塞砲の餌食にするつもりか、あるいは、我らに倍する大軍で我らを包囲し殲滅をはかるつもりか、どちらかの腹であろう。
だが、もちろん、我らとしては、大人しく敵の手中に落ちるわけにはいかぬ。
とはいえ、2倍の敵勢に真っ向勝負を挑むのは、危険が大きく、勝算も薄い。
当地には、我ら以外にも、ビルカパサに預けたインカ軍主力部隊が控えているのは皆も知っての通りだ。
このまま、その主力部隊と我らが分断させられたまま戦うことこそ、各個撃破を狙う敵の思う壺であろう。
それ故、今、我々が第一にすべきことは、一刻もはやく主力部隊との合流を果たすことである!
そのために、これから我らは、主力部隊と我らとの間に立ちはだかる敵勢3000の壁を突破せねばならぬ!!」
猛々しい表情で全軍の兵の隅々まで視線を馳せつつ、強い集中力をこちらに向けている若武者たちに己の言葉が浸透していくのを見極めながら、トゥパク・アマルは、敵の大軍を突き破る方法を、脳内でめまぐるしく模索する。

その身に深く息を吸い込み、トゥパク・アマルは語を継いだ。
「敵が戦闘隊形を完了してからでは、突破することは、いっそう難しくなる。
敵が移動中の今こそが好機!
即刻、我らも行動に移ろうぞ!!」
トゥパク・アマルの呼びかけに、ロレンソ軍の全軍の兵から、強い覇気が立ち昇った。
若々しく逞しい彼らのエネルギーをさらに高めるようにして、トゥパク・アマルが、なおも続けていく。
「この長かった反乱も、いよいよ大詰めにきている。
今宵、この砦を陥落させ、当地での戦いを制することは、この反乱の成否を大きく決定づけることになろう!
数百年にも及ぶ非道を極めた植民地体制の足枷を、今こそ断ち切ろうではないか!!
我らインカの父祖の大地に生きる全ての民を解放し、真の自由を勝ち取るために、重要なる布石をそなたたちの手で!!
そのためには、何としても、押し寄せる敵勢を、生きて、突破せよ!!」

「オー!!」
若き兵たちの鬨の声が、広大な大地の放つ荘厳な地鳴りのごとく、どこまでも勇壮に轟き渡っていく。
砦の上空にも、次第に雲が厚くかかりはじめている。
今しがたまで手元を明るく照らしてくれていた月光も、今はそれらの雲にさえぎられがちで、垂直に切り立った砦の石壁を登る難行をいっそう困難にさせていた。
しかし、闇が深まれば、それだけ、敵兵の目にもつきにくくなるはずだ。
(それに、もう少しだ…!!
あと少しで砦の屋上階に到達できる!
みんな、本当に、よく頑張ってくれた!)
全身、引っかき傷と汗だくになりながらも、アンドレスは、引き締めた口元を微かにほころばせた。
砦の頂上まで残すところ、あと5〜6メートル――!
ついにここまで這い上がってくることができたのも、ジェロニモや身軽な黒人兵たちの後押しと頼もしい援護があったからに他ならない。
いちはやく砦の上まで登り着いた彼らは、屋上階の砲台から累々と突き出された巨砲群の下に身を隠し、アンドレスの到達を息潜めて待っていた。
そうしながら、それらの要塞砲の頑強な砲頭に長いロープを縛り付け、それを石壁ぞいに下に垂らし、まだ壁面の途上にいるインカ兵たちがそれらを伝い登ってこられるようにしてくれていた。
憔悴の激しい者はそのロープを使いながら、一方、まだ自力で登る力のある者は己の手足で石壁を掴んで登りながら、皆、奥歯を食い縛り、滝のように汗を流しつつも仕上げの登攀に挑んでいる。

アンドレス自身もまた、水を浴びたように頭や額にはりついた髪から伝い落ちる無数の汗粒を、顔を振って吹き飛ばしながら、血の滲む両手足で石壁と懸命に取っ組んでいた。
そうしながら、強く気を引き締め直す。
(目標地点まで、あと僅か!
だけど、ここからが、今まで以上に危険なんだ。
いかに夜の闇が濃くなっているとはいえ、屋上に近づけば松明の火も赤々と燃えている。
あの屋上ぎわの手すりから、敵に覗き込まれたら、この近さじゃ俺たちの姿は丸見えだ…!)
ここからこそ慎重に慎重を期さねばならない――アンドレスは念を込めるようにして、己の目の前にある固く分厚い石壁に、傷だらけの拳をぐっと押し当てた。
その石壁を隔てた砦の内部では、マルセラが意識を失ったまま、巨体のスペイン兵に担がれながら、牢への薄暗い裏階段をくだっていた。
階下の奥まった場所にある牢までは、まだ大分距離がある。
にもかかわらず、そこに囚われたインカ兵たちの流す血の臭いまで漂ってくるような、鼻をつく淀んだ空気が充満している。
その狭い階段を、下の方から、別のスペイン兵が急ぎ足で上ってくる。
この裏階段の先には捕虜を収容する牢や古びた倉庫しかないため、牢の関係者以外、ここを通る者は殆ど無く、人通りも皆無に等しい。
それ故、今、下方から上がってくる兵もまた、恐らく、牢番の一人か誰かに違いない。
すれ違いざま、スペイン兵たち二人は、互いに短い言葉を交わした。
「その女を牢に戻しにいくのか?」
そう言ながら、上って来た足を軽く止めた兵もまた、厳ついガタイをした大柄な男であった。
二人とも中年より少し手前位かと見える年代で、よく見知った者同士のようである。
マルセラを担いだ兵も足を止めて、相手に問いかけた。
「そうだが、おまえは、屋上階に上がるのか?」
「ああ。
外の伏兵軍がトゥパク・アマルたちを砦の射程内まで追い込んだら、即座に砲撃できるよう、砲兵はもとより、手隙の者は皆、屋上砲台に召集されている。
牢内のインカ兵は、全員、のびちまっているから、あまり大人数の看守はいらないとさ。
それで、俺も上に呼び出されているのだ」
そう応じた兵が、相手のガッシリした肩に担ぎ上げられたままのマルセラに目をやった。
「その捕虜を運ぶの、おまえ一人で大丈夫か?」
その言葉に、巨躯の兵が、「俺を侮辱するのか?」とばかりに相手をギロリとひと睨みして、吐き捨てるように言い放った。
「こんな小娘一人、当然、俺だけで十分だ。
しかも、気を失っている上、武器も取りあげてある。
もっとも武器を隠し持っていたとしても、腕も拘束されたままでは、使いようもないだろうが」
「いや、そういう意味じゃなくて」と、上階に向かう兵が、気絶したマルセラの全身を舐めるように見回してから、ニヤリと相好を崩した。
「その女と二人きりで、おまえが、へんな気を起しちまわないかって、意味だ。
良く見ると、けっこう可愛いじゃないか」

「馬鹿な…!
インディオの女なんぞに興味は無い!」
マルセラを担ぎ上げたまま憤然と鼻息を荒げた兵に、もう一方の兵は、「ははは、冗談だ、ムキになるな」と、豪快に笑いながら階上へ消えていった。
再び、辺りに静けさが訪れる。
「こんな時に、何をふざけたことをぬかしてやがる!」
己の苛立った気持ちを吐き出すように、誰もいない空間に向かって怒鳴りつけると、また牢への階段を下りはじめた。
担ぎ上げられたマルセラは苦しげな息遣いをしながら、相変わらず意味不明なうわ言を唇から漏らし続けている。
『その女と二人きりで、おまえが、へんな気を起しちまわないかって、意味だ。
良く見ると、けっこう可愛いじゃないか』
先刻の兵の言葉が耳奥にこびりついているためか、先ほどまでは朽ちかけたズタ袋か何かを運んでいるのと変わらぬ感覚だったというのに、今は、その同じ捕虜の体が妙に生々しく感じられてくる。
「ったく、余計なことを言いやがって…!」
己の肩や背にグッタリもたれかかる女体の感触から意識を引き離そうと、兵は階段を下りる足を速めた。
と、その時、自分たち以外誰もいないはずの空間に、突如、切迫した大声が響き渡った。
「ロレンソ殿…!
来て…は…だめ!!」
突然のことに驚いた兵が、それが肩上の捕虜の放った言葉だと気付くまでに、数秒を要するほどだった。
同時に、マルセラ自身も、自分の発した声で、ハッと意識を取り戻した。

(ここは……?)
マルセラには、すぐには、今の状況が呑み込めない。
息詰まるような血生臭く、淀んだ空気。
まだ朦朧としたまま、瞳だけを動かしていく。
じめじめと湿気を帯びて苔むした石壁。
自分の足で歩いているわけでもないのに動いていく周囲の風景。
しかも、普段の自分の視点よりも大分高い位置から全てが見える。
(誰かに運ばれている…?)
まだ混濁した意識ながらも、自分が敵兵のがっしりした肩上に無造作に担がれ、牢へ続く狭い裏階段を下りているらしいと、おぼろげながらも掴めてくる。
かたや、スペイン兵の方は、マルセラを乗せたまま階段途中で足を止め、何かを反芻するようにブツブツ呟いている。
気を失ったままを装いながら、マルセラが兵の言葉に耳を欹てた。
「人騒がせな寝言をほざきやがって。
にしても、ロレンソだって?
どこかで聞き覚えのある名ではないか?
来るな、とは…?
あの麓のインカ軍の中に、その者がいるということか?」
今にも真相を探り当てそうな敵兵の言葉に、マルセラの心臓は、ドクンッ、と大きく跳ね上がった。
(まずい…!
私、とんでもないこと、口走ってしまったんだ…!)
ぼんやりとしていた意識が、一気にサーッと醒めていく。

階段を降りかけていた巨体を翻し、兵が再び屋上階へ向かって上りだしたのを感じ取って、マルセラの心臓はいよいよ飛び出さぬばかりに脈打ちだす。
(いけない!!
この兵、あのアレッチェに報告に行くつもりだわ!
アレッチェなら、きっと、すぐに全てを見抜いてしまう。
そんなことになったら、何もかも台無しよ…!
何とかして止めないと――!)
周囲を素早く見渡し、近くに他の敵兵がいないことを見届けると、咄嗟に、マルセラは兵の背の上でグイッと身をよじった。
そのまま重心を外側に傾けながら、ズルリと兵の背から、己の体をずり落とさせていく。
意図的に飛び降りたと思わせぬよう、兵自身が不注意で落としてしまったのだと思わせるよう――マルセラは、そう強く念じながら、自ら己の全身を地に崩れ落とさせた。
ドサァッ!!――鈍い音を発して彼女の体が地に落ち、と同時に、石段を勢いよく転がり落ちていく。

両手を後ろ手に縛られたままであったため、転落する体を止めるすべも持たず、ゴロゴロと派手に横転したすえ、十数段下の曲がり角に引っかかるようにして辛うじて止まった。
(いったぁ…!)
屋上階でアレッチェに痛めつけられた傷の疼きとあいまって、石段を転がり落ちた軋むような痛みは尋常ではない。
その激痛のために、思わず発しそうになった悲鳴を必死に噛み殺した。
あくまで意識を失ったままを装わねばならない。
崩れた体勢のまま、痛みに引きつる瞼を微かに見開いて、そうっと瞳だけを動かし、辺りを見渡す。
階段沿いの石壁には、ところどころ見張り用の覗き窓が備えられているが、夜間のためか、敵の侵入を防ぐためか、鉄扉がしっかり下ろされている。
人が一人ぐらいは通り抜けられそうな、その閉じた窓を見つめながら、戦士としてのマルセラの本能が、急速に甦っていく。
(砦の構造上、この裏階段沿いにある壁面は、海側方向に面しているはずだわ。
ということは、あの鉄窓の外の石壁を、アンドレス様たちの軍勢が登っているはず。
いや、もう、屋上階の方まで登りきっている頃か――)

一方、自分が急に方向展開した拍子にマルセラを落としてしまったのだと思ったのか、敵兵が焦り顔でこちらに振り向いた。
彼の視界の中で、石段を転がり落ちたマルセラは、横転して乱れた姿を晒しながら、ぐったり気を失ったままである。
捕虜が意識を取り戻していないことに安堵しながらも、慌てた足取りで、彼女に近づいていく。
「落としたのは、まずかったな。
こんなところで打ちどころでも悪くさせて、何かあったら面倒だ」
マルセラの体は、下り階段に沿って、いかにも不安定な状態で石段の上に横たわっていた。
頭の方が階段の下方にあり、足をこちらの段上に向ける形で、今にも滑り落ちそうな姿勢のまま、辛うじてそこに留まっている。
マルセラの足に引っかからないよう注意を払いながら腕を伸ばし、彼女の細い肩を掴み起そうとして、しかし、兵は、不覚にも、ゴクリと生唾を呑み込んだ。
石壁のところどころに灯る仄明るいランプの光が、階段に横たわるマルセラの肢体を濡れたように妖しく浮き上がらせている。
アレッチェの監視の目が光る緊迫した屋上階では気付くいとまもなかったが、今、目の前に無防備に全身を晒しているマルセラの姿は、視線を釘づけにさせずにはおかぬものだった。
いかにも戦士らしく鍛え上げられてはいるが、それだけに、かえって細っりとした女性的なラインが際立って、完璧な均整がとれている。
それは、目を奪われるほどの美しいプロポーションであった。

殊に、彼女を特徴づけるカモシカのような足は、スラリと引き締まりながらも、ほどよい肉づきがあり、若く瑞々しい褐色の肌とあいまって、まるでブロンズ像さながらの脚線美を成している。
機動性を増すためにマルセラ自身が短く切り上げた戦闘衣がめくれて、大腿部の付け根まで露わになったその足には、先刻のアレッチェに負わされた傷が随所で血を滲ませており、痛々しい以上に艶めかしくさえあった。
急速に己の身内に突き上げてくる抑えがたい欲望を振り払うように、宙に向かって兵が叫ぶ。
「馬鹿め…!
俺は何を考えて――」
己を叱咤し、さっさと担ぎ上げて先程のうわ言の報告に行かねばと、理性で厳しく言い聞かせた。
だが、吸い寄せられた彼の目は、眼前の女体から離すことができない。
マルセラの様子を探るように、男の目が、今度は彼女の顔の方へ動いていく。
黒く長い睫毛を伏せたまま、今も、完全に意識を失ったままである。
端正な顔立ちは、青年のような凛々しさを宿しながらも、傷ついた少女のように儚げであり、その透明感のある中性的な雰囲気が、かえって女性的な色香を増している。
兵はカラカラに乾いた己の唇を舐めると、いつしか、大柄な身をぐっと前に乗り出していた。
『その捕虜を運ぶの、おまえ一人で大丈夫か?
その女と二人きりで、おまえが、へんな気を起しちまわないかって、意味だ。
良く見ると、けっこう可愛いじゃないか』
ひやかしなのか警告なのか分からぬ先ほどの同僚の言葉が、どこか遠くの方で聞こえた気がした。
そして、己自身の中でも、遠い意識の果てで、不穏な何かを予見するかのように、警告音がせわしなく鳴り響いていることも。
しかし、それらの声も警笛も、無防備な獲物を前にして体の奥底から昂る強い渇望によって、あさっり掻き消された。

己のすぐ顔の下では、真紅の血に染まったマルセラの唇が、「う、ん……」と甘美に呻いて、形の良い胸が苦しげに反っていく。
ついに兵は堪え切れずに、薄暗い周囲にギラついた視線を走らせた。
相変わらず、辺りに人の気配は無い。
それを確認すると、ズズッと己の身を這わせ、倒れたままのマルセラの肢体の上に四つん這いになっていく。
「どうせ捕虜なのだ、少しぐらい良かろう。
女が後でなんと訴えようが、捕虜の戯言ということにすればいい」
欲情に上擦った声で低く呟くと、マルセラに覆い被さったまま、むさぼるように彼女の首筋に顔を埋めた。
――が、次の瞬間、兵の股間に、焼け付くような猛烈な激痛が走った。
「グワッ?!」
あまりの痛みに、その巨体が、高々と宙に飛び上がる。
と見るや、ただでさえ不安定な階段上にいたために、その体は大きくバランスを崩して、まるで横転した大砲のような激しさで階段を転がり落ちていく。
その上、頭が階段の下方側にあるマルセラの頭側に兵の頭部もきていたために、兵の巨躯は見事なほど鮮やかな勢いで頭から階下へ突っ込んでいった。

その一瞬の隙に、マルセラは、今、まさに相手の急所に渾身の膝蹴りを打ち込んだその足で、バッと立ち上がった。
両手を縛られていようとも、見かけに違わぬカモシカのごときバネを備えた強靭な脚力は、確かなものだった。
「このケダモノ!!」
そう叫ぶやいなや、階段の途中で頭から腹ばいに倒れ込んでいる兵の方へ、猛然と走っていく。
マルセラの一声に、謀られたのだと悟った兵が、殺気立って体を起しかけた。
しかし、兵が立ち上がるよりも早く、彼の真後ろに来ていたマルセラの顎の先端が、鋭いハンマーのごとく、背後から巨兵の首筋半ば――すなわち脊髄に向かって、正確に打ち下ろされる。
「グェ…――!」
声にならぬ呻きを上げて、気絶した兵の体が、ドゥッと、地に崩れ落ちた。
辺りに、急速に静けさが舞い戻る。
しばし息を大きく弾ませていたマルセラの口元から、恍惚と呟きが漏れた。
「やったわ……!」
両手を拘束されて武器も使えぬ彼女にとって、それは一か八かの大きな賭けでもあったのだ。
マルセラ自身も信じられぬ思いで、まだ呆然としながら、その場に立ち尽くしている。
(クスコ戦の時に身に付けた不殺の技が、こんなところで役立つなんて…!)

数秒の後、我を取り戻したマルセラは、身動きしなくなった巨人のような敵兵の全身を改めて見下ろした。
完全に気を失っていることを良く確かめてから、彼女は後ろ手に縛られた両手の指先を器用に使って、敵兵の腰に結び付けられた地下牢の鍵を奪い取った。
「これで地下牢に繋がれた仲間たちを助けられる」
そう囁いて己に頷き、「さあ、急がないと!」と、素早く踵を返した。
それから、先ほどから目に留めていた覗き窓の傍へ駆け寄っていく。
その窓の前で立ち止まると、今度は、無意識に溜息が漏れた。
何をおいても敵を倒すことのみに集中していた全神経が次第に解れていくにつれ、ぞっとするような居た堪れぬ思いが沸き上ってくる。
「あんなやり方、最悪だ……!
女を武器にするようなことをしちゃったなんて…!
でも、他に方法が無かった――」
マルセラは震える瞼を伏せ、今も血の滲む唇を噛み締めた。
(それに…あんなこと、ロレンソ殿にだって……)
そう思うと悔しさに涙が込み上げそうになったが、今は、それどころではなかった。
アレッチェの猛打によって負わされた傷も、一挙一動ごとに全身が軋むばかりに痛んだが、それも構っている場合ではなかった。
様々な悪いものを全て振り払うように激しく首を振って、走り寄った鉄窓の様子を鋭い横顔で観察する。
(この覗き窓の向うに、石壁を登っている仲間たちがいるかもしれない!)
窓に集中するマルセラの瞳が、真剣さを増していく。
鉄扉で閉ざされた窓には、上下にスライドする鉄製の閂(かんぬき)が下ろされ、施錠されていた。
だが、それは外部から開けることは不可能でも、内側から開くのは、そう難儀ではない構造のものだった。

周囲の気配に目と耳と全神経を研ぎ澄ませながら、その閂を口でくわえて、グイッ、と下から上へ力一杯に押し上げていく。
なにしろ、いまだに両腕は背後で縛られたままなのだから、そうするしか方法が無かったのだ。
切れた唇から滲む血の味と閂の鉄の味とが口中で混ざり合い、うっと嘔気が込み上げる。
それでも堪えて押し上げるうち、やがて、ガタンッ、と衝撃がひとつあって、同時に唇にかかっていた重みが消えた。
(閂がはずれた!)
もうひと息、マルセラは顔全体に力を込め、今度は額を使って鉄窓を外に押しはじめた。
ギイイ、と鈍い軋み音をあげながら、窓が開いていく。
――サアッ…。
涼やかな夜の冷気と共に、潮の香りが流れ込んだ。
黒髪を優しくなでて通り過ぎる風にのって、潮騒の音さえ聞こえてくる。
血生臭く淀んだ空気の中にいただけに、生き返るような清涼な潮風に、マルセラは我知らず顔を輝かせた。
(ああ、なんて気持ちがいいの!!)

大きく深呼吸をすると、窓から身を乗り出した。
自分のいる場所は、高さにすれば地上と最上階のちょうど半ば辺り、建物全体の末端付近の位置らしく、石壁を高所まで登っているに違いないアンドレス隊の姿は、すぐには見つけることができなかった。
が、それでも、砦の石壁の上方を振り仰ぎながら、さらに大きく身を乗り出していくと、壁の随所で見張りをしているインカ兵の一人を、ついに視認することができた。
その兵さえも、自分の居る場所からは遥か高所にいたが、そちらに向かって、ピョッと鋭く一吹き、夜鳴き鳥の声に似せた口笛を鳴らすと、はっと、相手がこちらを振り向いた。
かなり離れた位置、しかも、夜間ではあったが、マルセラの開け放った窓から漏れるカンテラの仄かな灯りが目を引き付けたのか、警戒を強めながらも、こちらを注視している。
ほどなく、その野性の視力を備えたインカ兵は、懸命に窓から上半身を振って我が身の存在を訴えているマルセラの姿に気付いてくれた。
彼は「信じられない!」と驚嘆したように幾度も頭を振っていたが、すぐに他の数名のインカ兵と共にロープを伝って石壁を滑り下りて来た。
「マルセラ様?!
なんと、ご無事で!!」
「マルセラ様、ああ、ほんとに本物のマルセラ様じゃないですか!!」
昂る興奮と歓喜を隠せぬインカ兵たちが口々に叫ぶ。
「シ、シーッ!
敵に気付かれてしまうわ」
慌てて兵たちを制しながらも、マルセラも湧き上がる喜びに明るい笑顔を輝かせた。
「みんな、ごめん!
心配をかけてしまって!」
「まだ信じられませんよ!!
良かった…今度ばかりは、どうなるかと思いました……!」
「うん…ごめん、本当に…!」
窓辺で合流を果たしたインカ兵とマルセラたちが、感極まって、涙声を発し合う。

そのうちの数名の兵が、「アンドレス様に、すぐにご無事を知らせてきます!」と、嬉々として、ロープ伝いに石壁を登りはじめた。
それらの兵たちを見上げて、マルセラが急いで声をかける。
「屋上階には、物凄い数の要塞砲が据えられているわ。
それに、砲弾を焼く大釜まであって、それに火も入ってる。
砦へ進軍する麓のインカ軍を灼弾で焼き殺そうとしているの!
武装した敵兵も多数結集しているから、アンドレス様たちに、くれぐれも用心してと!」
マルセラの言葉に、「了解!」と敬礼を返して、兵たちが砦の上方へ素敏(すばしこ)い動作で消えていく。
残りの兵たちが、すかさず窓から砦の内部に滑り込んできて、マルセラの縄を解いた。
それから、改めて互いに抱き合い、再会を喜び合った。
「それにしたって、なんて痛々しい姿ですか。
どこもかしこも傷だらけじゃないですか!」
「こんなの、ただの掠り傷よ」
そう言って意気揚々と胸を張って見せたマルセラだが、次の瞬間、腹部を押さえて「アタタタ…」と、石床に蹲(うずくま)った。
「大丈夫ですか?!」
心配そうに自分を支える兵たちに、マルセラは俯かせた顔をゆっくり上げる。
「情けないよね…こんな姿――。
でも、みんなに会えたから、今は痛みもずっと楽に感じるし、もう本当に大丈夫だって気分なの。
一時は、マジで、どうなるかと思ったけどね。
みんなとまたこうして一緒になれて、すごく嬉しいわ」
素直にそう言って微笑んだマルセラに、周りのインカ兵たちも胸熱くしながら笑顔を零した。

ほどなく彼女はスックと立ち上がると、戦士の顔に戻って、深い縄跡の残る手首を揉みほぐしながら問う。
「それで、アンドレス様の状況は?」
「砦の頂上階まで到達しており、すぐにも、手すりを越えて乗り込もうというところです」
力強い面差しで応えた兵に、「そう!」と、マルセラも凛々しい眼差しで頷いた。
「この窓からも、砦の内部に侵入できるわ。
もっとも、すぐに敵兵たちが嗅ぎ付けて、やってくるでしょうけど。
それに、私と一緒に囚われて牢内にいる仲間たちも、助けださなければ!」
紅々と無数の松明が燃える砦の屋上階――。
砲弾を焼く大釜から立ち昇る白い湯気が、黒々とした夜空にモウモウと広がっていく。
その屋上階に布陣したスペイン兵たちは隙の無い砲撃態勢を整え、砦外に配備した大規模な友軍によってトゥパク・アマルたちが射程内に追い込まれてくるのをジリジリと待ち受けている。
スペイン軍総指揮官アレッチェは、屋上砲台中央部に立ち、その高所から敵味方全体の動きを俯瞰している。
そうしながらも、先刻来、己の心にずっと引っかかってならないマルセラのうわ言を、胸の内で執拗に反芻していた。
『…ロレ……ソ…ど――。
――来…は…だ……』
意識を失っていながらも呟き続けていた意味不明のあの言葉は、何を言おうとしていたのか。
自分たちが見落としている重要な何かが、その言葉の裏に隠されているように思えてならなかった。
松明の火に赤黒く照らし出されたアレッチェの彫の深い横顔で、眉間にきつく皺が寄っていく。
(うわ言とはいえ、あの状況であれば、誰かに何かを訴えようとしていたのではないか?
ならば、『ロレ……ソ…ど――』とは、誰か人の名前ではないのか?)
不意に振り向いたアレッチェの鋭利な視線が、隣に控えるサルセードに突き刺さる。
「サルセード大佐、『ロ、レ、ソ、ド』のつくようなインカ兵の名に、聞き覚えはないか?」
「ロ、レ、ソ、ド、がつくインカ兵でございますか?!」
いきなりのことにサルセードが目をパチクリさせながらも、アレッチェの険しい眼差しに押されて、咄嗟に懐から手帳の束を取り出した。
それを、唾を塗りつけた太い指先で慌ただしく繰りながら、ほどなくブンブン首を縦に振った。
「ええと、はい、閣下!
似たような字面を持つ名の者が、確かに、おりますぞ!
『ロレンソ』という兵でございます!!」

アレッチェの眼光が鋭さを増した。
「ロレンソ?」
そういえば耳にしたことがあるような、と眉根をさらに寄せながら、「どのような人物だ?」と、口早に問い質す。
「はっ、閣下。
記録によれば、反乱初期の頃から反乱軍に加わって、今ではトゥパク・アマルの重側近の一人ともなっている若いインカ兵です。
若年ながらインカ軍を率いる将兵の一人。
出身はクスコで、インカ貴族の末裔。
性格は、きわめて冷静沈着。
あのアンドレスの学友でもあり、現在も二人はかなり懇意な仲にあります」
サルセードの言葉が終る前に、アレッチェの口から「やはりそうか…!」と、憎々しげな呻きが漏れた。
「これで全て読めたぞ。
あの若造どもの軍団の将兵、どうりで、アンドレスらしからぬ様子だと、訝しく思っておったのだ。
いつもの血気に逸ったアンドレスにしては、不自然なほど抑制が利いていたのも当然だ。
全くの別人だったのだからな。
『アンドレス』の軍勢などと、我らをたばかりおって……!
実のところは、アンドレスと似た年恰好のロレンソなる影武者を陣頭に立たせた、偽装軍団だったのだ」
「えっ…!!」
サルセードや周囲のスペイン兵たちが即座には理解しきれず息を呑む中、ギリギリと拳を握り締めるアレッチェが、鬼のような形相で轟然と叫んだ。
「探せ!!
我らがまんまと騙されている間に、本物のアンドレスが、今しも、この砦のどこかから侵入を図ろうとしているに相違あるまい!
砦の四方八方を徹底的に探せ!!
この砦に、蟻の子一匹、入れさせてはならん!!」

アンドレス率いる侵入者たちを探して、海側手すりにも、ドッと、スペイン兵たちが群がっていく。
その頃には、響きくるアレッチェの言葉を聞きつけて、アンドレス隊の兵たちは、速攻、4〜5メートル下方まで砦の石壁を伝い降りていた。
そのまま壁にピッタリ体を寄せて、身を潜めた獣のように息を殺し、濃い夜闇に全身を溶け込ませている。
そんな彼らの姿は、手すりから覗き込んだ敵兵たちの目には、すぐには留められることはなかった。
しかし、それも、ほんの僅かな間のことだった。
「こっちには誰もいないぞ!」
「もっと下まで、よく見るんだ!!」
「いくらなんでも、こんな絶壁みたいなところを登ってくる奴はいないだろう?!」
「いや、砦の山側に我らを引き付けたのは、その反対側のこちらから侵入しようって腹があったからに違いねえ!」
スペイン兵たちは口々に言い合いながら、ランプを手に、さらに身を深く乗り出して下方を覗き込む。
ほどなく、数名のスペイン兵が、幾つもの要塞砲の砲身に結び付けられた何本ものロープを発見して、憤激の声を荒げた。
「見ろ!!
俺たちの大砲にロープまで結び付けていやがる!!」
「インカ兵どもの仕業に違いねえ!!」
「くっそお、俺たちの声を聞きつけて、逃げちまったんじゃねえのか?!」
いよいよヒートアップしながら、高まる激昂と興奮にがなり合う敵兵たちの群がりによって、海側手すりは鈴なりになっていく。
「鼠どもめ!!
絶対に捕まえてやる!!」
「もっとデカいランプを持って来い!!」
そう叫んで取り寄せた大型ランプに、今度はロープを繋いで、それを手すりから砦の石壁沿いにジワジワと下ろしていく。
その仄明るいランプの光に照らされて、突如、「アッカンベー!」をした黒人兵の顔が、下方から浮かび上がった。
「うわっ!?」
スペイン兵たちが素っ頓狂な声を上げて反射的に銃を構えた瞬間、ランプを握っていた敵兵の顔に、いきなり握りこぶし大の玉がブチ当たってきた。
と思いきや、その白球が顔面上で炸裂。
その中に詰まっていた白っぽい粉が、ブワアッ、と大気中に飛散した。
それら目潰しのような粉末が、周囲の敵兵たちにも容赦なく振りかかる。
さらに、その一発を皮切りに、長大な海側手すりの全域で、一斉に砦の下方から無数の白球が飛んできて、覗き込んでいたスペイン兵たちの顔や体に激突していく。
目や口を押さえて咳き込む彼らに追い打ちをかけるように、天高く、凛然とした若者の号令が猛々しく響き渡った。
「今だ!!
いけえ!!
もっと投げ放てえ!!」
そのアンドレスの雄叫びを機に、さらに激しさを増して、手すりの下方から屋上のスペイン兵に向かって、続々と投げ込まれくる無数の白球。
砦の石壁に張り付いたまま、インカ兵や黒人兵たちが、背負っていた袋から取り出した何かの球を、息もつかせぬ勢いで狂ったように投げ付けてくるのだった。

強烈な勢いで何百と飛んできて、ブチ当たりくる、それらの球を浴びるスペイン兵たちは、その顔も、頭髪も、軍服も、何もかも、炸裂した球から弾け飛ぶ粉末で、みるみる真っ白に染まっていく。
しかも、辺り中に飛散した粉が目に染みて、薄く目を開けていることすらままならない。
その上、それらの粉末は、夜の大気中に、広く、濃く、拡散して、たちまち屋上階全域を茫漠たる白い煙幕で覆い包んでいく。
咄嗟に片手で鼻と口を覆いながら、もう片手で白煙を払うアレッチェの傍で、全身に雪を被ったような姿のスペイン兵が、粉末の染みた目から涙を落としつつ、激しくゲホゲホやっている。
その兵が、石床に飛散した卵の殻や白粉を憎々しげに踏み潰し、むせかえりながら叫んだ。
「アレッチェ様!!
こいつは、前にもインカ兵がクスコの広場で使ったヤツと同じです…!
単に小麦粉を詰めただけの爆弾…こんな子供騙しの……!」
それ以上は、吸い込んだ粉末が大量に喉に詰まったらしく、言葉にならなかった。
その兵の言葉を待つまでもなく、インカ兵が投げつけたものは、乾燥させた鶏卵の殻に空けた穴から小麦粉か何かの粉を詰めただけのものにすぎないと、アレッチェ自身も早々に見抜いていた。
今の兵は「爆弾」などと呼んだが、実際には、火薬のひとつまみすら入ってはいまい。
だが、いかに原始的な代物とはいえ、その目潰しと煙幕の効果は、即座には防ぎようのない強烈なものだった。
口や鼻を押さえながらアレッチェが睨み上げた数十メートル先では、白々と霞む濃い煙幕の向うに、若いインカ兵の輪郭が浮かび上がっている。
そのインカ兵――正確には、インカ族とスペイン人の混血児だが――は、既に手すりと、そこに据えられた海側砲台を乗り越えて、屋上階の内部に侵入していた。
彼は、白と黒の市松模様の貫頭衣に、幾何学模様の織り込まれた飾り帯を締め、革製の胸甲を身に付けている。
それは、他のインカ兵たちと同じ、インカの伝統的な一兵卒の装束であった。
その戦闘衣に白い粉を降り積もらせながら、それら自分たちが放った粉末や煙幕による実害を避けるためであろう、ゴーグルとマスクまで着用している。
もっとも、「ゴーグル」とは言っても、何かの動物の皮に丸いガラスを二個はめて、それを頭の後ろできっちり結んでいるだけの、これまた原始的なものではあったが。
それらによって顔の全容はほぼ隠され、身なりも素朴なものではあったが、それでも、粉混じりの夜風に栗色の髪をなびかせ、長い足ですっくとそこに立つ、その長身の背格好や纏う雰囲気には、明らかに見覚えがあった。
その混血児とアレッチェ――彼ら二人は、暫しの距離を隔てながらも真直ぐに対峙し、ぶつけ合う視線で早くも火花を散らしている。
「よく来たな、アンドレス」
噛み締めた歯の隙間から、アレッチェの苦々しい声が低く漏れた。
対するアンドレスも、込み上げる感情を押し殺した声で、重々しく言い放つ。
「アレッチェ、やっとおまえに会えた」

さらに、そのアンドレスを中心に、海側手すりぎわにズラリと並んで、予断無く銃を構えた多数のインカ兵や黒人兵たち。
この場にいるスペイン兵たちよりも数的に少数とはいえ、ザッと見渡しても、300人以上はいると思われた。
「よくもまあ、これだけの大人数をこのような砦の上まで這い上がらせたものだ」
皮相感たっぷりにアレッチェが言い捨てた脇で、滝のような涙と鼻水の止まらぬサルセード大佐が、呂律の回らぬ声で喘ぎ喘ぎ言う。
「閣下…ゴホッ!
あやつら、我らの要塞砲にロープまれ巻き付けていたようれあります。
それれ、あんなに大勢の兵を…!」
そんなサルセードには一瞥もくれず、アレッチェが煙幕を払いながら見据える先では、敵兵たちは皆、自らの放った粉末で全身を白く染め上げながらも、アンドレスと同様、呼吸と視界をゴーグルとマスクでしっかり防御している。
その姿を冷ややかに眺めながら、アレッチェは苦笑を洩らした。
そもそも、この急峻な砦の石壁を登ってこようなどと考えること自体、正気の沙汰ではないが、それを実行に移すなど、どれだけ無駄な徒労を要したことか。
その上、このような「小麦粉爆弾」を用いての侵入――。
原始的とうよりも、むしろ幼稚とさえ思える手段を、命懸けで生真面目に実行している目前のインカ兵たちが、あまりに滑稽で、愚かしく、子供じみて思えてならなかった。
それと共に、そのような素人くさい手に甘んじた己らが、嘆かわしいやら、それすら通り越して可笑しいやらで、冷笑が込み上げずにはいられなかったのだ。

その時、不意に、屋上階の随所で、閃光が瞬き、数発の銃声が弾けた。
アレッチェが、すかさず、そちらを振り向く。
スペイン兵が、インカ兵に向かって、やみくもに発砲しだしたのだ。
視界がひどく悪い中、無理矢理に狙撃しようとするために、誤って味方撃ちをしている者も少なくない。
逆に、アンドレスをはじめとしたインカ兵たちは、野獣のような敏捷さで、むせかえるスペイン兵の群れに身を紛らせ、狙いの定まらぬ銃弾をかわしている。
それら敵兵の陰から、黒人兵たちは相変わらず大量の「小麦粉爆弾」を、さらにはインカ兵たちは懐に巻き付けていたオンダ(インカ時代から続く投石器)の棘ばった石を、銃撃してくる白人兵に向かって怒涛の勢いで投げつけている。
いかに簡素な飛び道具とはいえ、鉄鎧さえも突き破る威力のあるインカのオンダは、侮れない。
猛獣の巣をつついたような喧騒に煽られ舞い上がる白粉に血飛沫が弾け飛び、と同時に、強い硝煙の臭いが充満し、そこにいる者たち全ての神経を逆なでする。
その騒然たる屋上階の空間に、アンドレスの声が断固とした口調で響き渡った。
「アレッチェ!!
すぐに銃撃をやめさせろ!!」
ゴーグルに隠されたアンドレスの目は見えないが、琥珀色の双瞼が貫くように己を睨み据えていようことは、アレッチェには容易く想像がついた。
「やめさせろ――。
でなければ、こちらからも銃を使う」
今度は凄むように低く言ったアンドレスの全身を、アレッチェの冷徹な両眼が鋭く検分する。
その若いインカの将兵の腰には、これまでの戦場で幾度となく不気味な威力を見せつけられてきた、あの重厚な長剣が吊られている。
そして、その剣帯に差し込まれていた拳銃は、今、アンドレスの手の中に収まって、きっちり己の方に狙い定められていた。

さらに横目で素早く見渡せば、己らを取り囲むインカ兵たちも既に銃口をこちらに向けて、即座に発砲できる用意を整えている。
インカ兵たちが撃鉄を起す音まで聞こえてきそうな張り詰めた空気の中、アレッチェの唇が、気だるそうに僅かに動いた。
「撃つのをやめさせろ」
短く命じたアレッチェの言葉に、傍らのサルセードが、「え?!」と、白目を剥いて喉を詰まらせる。
「大佐、聞こえんのか。
我が軍の兵に、銃撃をやめさせるのだ」
有無を言わさぬアレッチェの厳しい声音に、サルセードは、「はっ!」と、慌てて恭順を示し、あたふたと後ずさった。
確かに――いかに射撃の腕の未熟なインカ兵たちとはいえ、このような至近距離で、ゴーグルに守られた精度の高い視界の中で銃撃を行えば、多大な被害を受けるのは自軍の方であろうということは、サルセードにも分かった。
スペイン兵たちに発砲停止を命じながら、サルセードは、アレッチェの胸の内を推し量る。
(多分、閣下は、この白粉の煙幕が晴れるまで、時間を稼ごうとしておられるのだ。
視界さえ晴れれば、インカ兵なぞ、一斉掃射してしまえば一溜まりもあるまい。
むこうが反撃に出ようが、素人集団のインカ兵の銃撃など、猿真似も同然。
熟練した我が軍勢の腕に敵(かな)おうはずがない。
増してや、この至近距離なら、なおさらだ)
サルセードは、ズズッ、と大きく鼻をすすりあげ、血走った目の端でアンドレスの方を呪わしげに見やった。
(あの小生意気な混血の青二才めが、今に目にもの見るがいい)
一方、サルセードが密かに己を毒づいていることなど知る由もないアンドレスは、「よし!」と、力強く頷いた。
アレッチェの命令で敵の銃撃がやんだのを見届けると、彼も味方の兵に、きっぱりと命じた。
「攻撃停止!!
オンダ(投石器)も、球も、放つのをやめよ!」
その号に俊敏に反応して、インカ兵も、黒人兵も、オンダや白球を投げつけていた動きを瞬時に止めた。
屋上階の空間に、不気味な静けさが訪れた。
だが、睨み合うアンドレス隊とスペイン兵の間には、ますます一触即発の緊迫した空気が漲っている。
両軍の間に濃密に立ち込めていた白い煙幕が、夜風に流され、次第に視界が晴れていく。
アレッチェにピタリと照準を合わせた拳銃を微動だにせぬまま、アンドレスが、ゴーグルとマスクを脱ぎ去った。

インカ族らしい野性味とスペイン人らしい優美さを兼ね備えた、彫像のような端正な風貌が現れる。
風になびく柔らかい栗色の前髪の間から、月光を反射して閃光を放つ琥珀色の瞳が見え隠れしている。
険しい表情にもかかわらず、その甘いマスクは、この場にあってもなお優しい印象さえ与えるが、それでいて、成長と共に着実に精悍さも増していた。
トゥパク・アマルの類縁だけあって、どこかトゥパク・アマルにも似たその風貌を、冷厳な面差しで見やるアレッチェの視界の先で、アンドレスがスゥッと深く息を吸い込んだ。
と見るや、広大な屋上階全体に響き渡る大音声で、次なる号令を放った。
「あれを撒(ま)け!!」
視界が晴れる前に事を推し進めようとしているのが明らかな、口早で、それでいて、猛々しい号令が、屋上階全体にこだまする。
そのアンドレスの号に即応して、屋上階の広範囲に散開していた、ひときわ大柄なインカ兵たちが数十名、ザッ、と隊列の中から力強い一歩を踏み出した。
それら巨躯の兵たちは、各々、逞しい背中に厚手の皮袋を背負っている。
それをドサリと床に下ろしたかと思いきや、いきなり中のものを屋上階の石床に向かって投げ放ったのだった。
ザバアッ、と大きく水音が弾ける。
袋の中から、黒っぽい液体が広範囲に飛び散った。
と同時に、鼻を突く異様な臭いが、辺り一面に立ち込める。
「――!」
己の足元までジワジワと流れ来る、粘り気のある黒っぽい液体――。
アレッチェの目元が、ピクッと、一瞬、引きつった。
「う、これは――」
受け容れがたい現実を拒むように、まだ己の足元に広がりゆく液体から目を離せずにいるアレッチェの耳に、感情を押し殺した平板なアンドレスの声が聞こえてくる。
「お察しのとおり、原油だ」
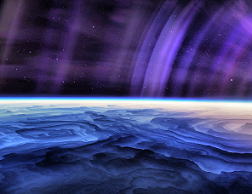
「――っ…!」
反射的に険しい表情を上げたアレッチェの周囲で、サルセードやスペイン兵たちからも、ドッと、大きなどよめきが上がった。
慄(おのの)きとも罵声ともとれる、そのどよめきを貫いて、アンドレスの鋭い声が断固たる口調で響き渡る。
「動くな!!
俺自身だろうが、この中の俺たちの誰だろうが、一人でも狙撃されることがあれば、我らの部隊の中の誰かが、瞬時に、ここに撒いた油に火を放つ!」
その言葉を証明するかのように、アンドレスの脇に立つ黒人青年ジェロニモが、たっぷり原油を染み込ませた布を巻いた松明を、ニッコリ笑って一振りした。
彼は、艶やかな黒い手で太い松明をガッチリ握ったまま、それを砦に据えられた篝火(かがりび)にゆっくり近づけていく。
原油だけあって、引火するまでに若干の間があるも、ほどなく、彼の手にある松明上部に、ボッ、と赤黒い炎が燃え上がった。

さらに、ジェロニモは、その松明を振りながら、「見てご覧!」とでも言わぬばかりに、屋上階の方々を笑顔で指し示す。
目元を歪めたアレッチェらが、ジェロニモの松明の動きを視線で追う。
案の定、その屋上階の随所にて、ジェロニモと同じような燃える松明を掲げ上げたインカ兵たちが、いつでも床の油に向かって投げ放てるよう、点火の準備を整え済みでいる。
それらインカ兵たちの様子と、床に大きく広がっている黒い液体と、それから、アンドレスとを、順にひとしきり見渡してから、アレッチェが、ふっと、溜息とも息継ぎともとれる息を吐いた。
彼の表情は口惜しげではあったが、それでも、さすがに取り乱すことは無く、その声音も冷厳である。
「おまえたちの要求は何だ、アンドレス」
海側手すりに近い位置にいるアンドレスと、広々とした屋上階の中央付近にいるアレッチェとの距離は、ざっと20メートル以上はあろうか。
周囲の敵兵による不意の攻撃に神経を張り巡らせながらも、アンドレスは唇を引き結んだ鋭利な表情を、ぐっ、と上げた。
アンドレスとアレッチェ――互いを刺し貫く鋭い矢のごとき視線が、激しくぶつかり合う。
「言うまでも無い!
おまえたちに、今すぐにも、この国から出て行ってもらうことだ!!」
相手から1ミリも視線を外さず、決然とアンドレスが答える。

対するアレッチェは、口端を吊り上げ、冷やかな苦笑を浮かべた。
「それは、また、たいそうな要求だな。
アンドレス」
強い緊迫感を漲らせた両軍の間を、いよいよ張り詰めた緊張が、ビリビリと電流のごとく走り抜けていく。
その空気を引き裂くように、アレッチェの抑揚の無い硬質な声が響き渡る。
「当然ながら、そのような要求を受け入れることはできない。
まさか、これしきのことで、そんな馬鹿げた話が通ると本気で思ってはおるまいな」
己を小馬鹿にするかのようなアレッチェの皮相な態度にも動ずることなく、アンドレスは真面目な表情を変えぬまま、今一度、大音声を張った。
「では、ひとまず、この砦を頂こうか!
アレッチェ、おまえの方こそ、この状況を楽観するのは賢明ではなかろう。
神かけて、これは単なる脅しではない!
おまえたちの中に、どれほど多くの犠牲者がでようとも、おまえの返答ひとつで、俺たちはいつでも放火する準備がある」
それを、アレッチェが、またも鼻であしらう。
「この砦を渡せだと?
たかが、ここに油を撒いてみせた程度で、戯言(たわごと)も大概にしたらどうだ。
仮に、ここにいる我らが、おまえたちの放った火で焼死しようとも、この砦を、おまえたちの手に渡してしまうよりは遥かにマシだろうよ」
「――なんと、これは驚いたな!」
アンドレスは、本気で、大きな瞳をしばたたかせた。
「アレッチェ、おまえの口から、そのような美談を聞けるとは!
砦を守るためならば、己の身は犠牲にしてもかまわない、そう言うのか?
本気なのか?
おまえだけでなく、ここにいる、おまえの何百という部下の命を共に犠牲にすることもいとわぬと、本気で言っているのか?」

アンドレスの眼光が次第に険しさを強め、声には有無を言わさぬ凄みが増していく。
かたやアレッチェは、目の端をギリギリと吊り上げながらも、相変わらず、その態度は、傲慢でふてぶてしい。
「幾度も言わせるな、アンドレス。
我らは、おまえたちに砦を明け渡すぐらいなら、ここで丸焼けになる方がマシだと言っている」
「あくまで、そう言い張るか――」
アンドレスは、己の気を鎮めるように深く息を吸い込むと、さらに語を継いだ。
「アレッチェ、おまえがそこまで言うのなら、あと一歩だけ、俺たちにも譲歩する余地がある。
この砦を全て、というのが気に入らないというのならば、その物騒な大砲たちをまるごと、要するに、この屋上階全体を頂こうか!
だが、いいか、これ以上の譲歩は、もはや無いと言っておく!!」
再びアレッチェが口を開こうとする前に、アンドレスが断固たる口調で、それを遮った。
「おまえたちに、それを拒むことはできない。
おまえたちに残された選択肢は二つに一つ。
おまえたち自ら、この屋上階から即座に退却するか、それとも、ここに居座って、火の海の中で焼け死ぬか、そのどちらかだ!
砦を守るために、ここで部下たちと共に壮烈なる殉職を遂げたいというのならば、俺は止めない。
好きにするがいい。
選ぶのは、おまえたちだ。
だが、早く決めろ!
俺たちも、もうこれ以上、一刻も待てない!!」

アンドレスは松明の炎を反射して赤銅色に光る瞳を動かし、今も灼弾を熱している大釜を一瞥した。
「おまえたちが英国艦隊を焼き尽くし、俺たちの仲間をも焼き殺そうとした、あの釜のおかげで、さぞ、ここにも良く火が回ることだろう」
対するアレッチェは、冷厳な表情を崩さないながらも、吊り上がった目元は、さらに険しく聳(そび)やかされていく。
そのような彼の周囲では、サルセード大佐をはじめ、大勢のスペイン兵たちが、すり鉢を擦り合わせるように強く歯軋りしながら、アレッチェの決断とアンドレスの出方に息を詰めている。
その間にも、背負ってきた原油を続々と投げ放つインカ兵たちの手によって、辺りには、ますます鼻を突く悪臭が充満し、嘔気を誘うほどになっていた。
異様に張り詰めた空気と悪臭の中、アレッチェの冷厳な声が響き渡る。
「なるほど。
アンドレス、おまえの要求はよく分かった。
とはいえ、この場所や要塞砲を奪い取ったとして、そのような物騒な火など放てば、おまえたちとて、ここを使えなくなってしまうではないか」
間髪入れず、アンドレスが相手を睨みつけたまま、言い放つ。
「そのような心配は、して頂かなくて結構だ。
俺たちは、今、この要塞砲群を無力化できれば、まずはそれでいい。

これ以上、余計なおしゃべりは無用だ!
あと一分以内に、おまえの兵を、全員、ここから退(ひ)かせろ!!
一分だ!!」
アンドレスは、右手に銃を構えたまま、左手で傍らのジェロニモから松明をガッチリ受け取ると、最後通牒を突きつけるように決然と叫んだ。
その時だった。
アンドレスの言葉と重なるようにして、砦の階下から屋上階へ続く中央昇降口の鉄扉が、バンッ、と猛烈な勢いで跳ね開けられた。
ちょうどアレッチェの近くにあったその中央扉から、スペイン衛兵が血相を変えて飛び出してきたのだ。
兵は半ば叫ぶように報告する。
「アレッチェ様、大変であります!!
砦の内部に敵兵が侵入しております!
施錠していたはずの鉄窓が幾つも開かれて…!
あの女の捕虜が脱走をはかり、敵兵を誘導したものかと!!」
そこまで一息に言ってから、その衛兵は屋上階で展開している状況に気付き、さらに蒼白になって目を剥いた。
当の衛兵自身の足元にも、はやくも黒い液体が押し寄せてきている。
「こ、これは…?!」
「原油だとさ。
おまえも、ここにいると、その染みた足元から丸焼けにされるぞ。
我々に残された時間は、あと30秒を切っている頃だろうからな」
衛兵に向かってか、己自身に向かってか、アレッチェが反吐を吐くように言い捨てると、同時に、彼は原油にまみれた石床にペッと唾を吐きつけた。
と見るや、それが合図であったかのように、屋上階に散開していたスペイン兵たちが、再び瞬時に銃を身構え、インカ兵たちに向かって一斉に発砲したのだ。

「アンドレス様、危ない!!」
敵が銃を構えた瞬間にアンドレスを守って彼の前に身を投げ出したインカ兵の体から、大量の血飛沫が噴き出した。
そのまま床に崩れゆく兵の姿を見つめるアンドレスの瞳が、わななきながら愕然と見開かれていく。
「――!」
その間にも、不意打ちの敵弾を喰らった多数のインカ兵や黒人兵が、人形のようにバタバタと倒れゆく。
厳しく訓練されたアレッチェ麾下の兵たちは、銃撃の一瞬のチャンスに備えることを忘れてはいなかったのだ。
アレッチェは、アンドレスとの冗長な対話で時間を稼ぎ、視界の晴れるタイミングを待って、自軍の兵に暗黙のサインを発していたのに相違ない。
衝撃に身を凍りつかせたアンドレスを庇いつつ、ジェロニモが、アンドレスの手にある松明を半ば毟るように取り戻した。
「アンドレス様!!
火を放つことをお許しください!!」
ジェロニモは、その松明を、石床に向かって猛然と投げつける。
が、それよりも早く、敵弾を受けて倒れた多数のインカ兵が手にしていた松明の炎が、方々で床の原油に着火していた。

まるで焔の小悪魔が次第に大魔王の姿へ肥大化していくかのように、初めは緩慢に、しかし着実に速度を増しながら、炎の舌が屋上階全域を席捲(せっけん)していく。
火災の拡大に伴い、ますます原油は高熱を帯び、それにつれて、さらに業火の規模も、速度も、激化していく。
屋上階に火薬庫は据えられてはいなかったものの、幾つも置かれていた火薬桶や、灼弾を焼く大釜にも火が回り、屋上階の随所で続々と小爆発が起こった。
轟音と共に手すりや石床の数か所が派手に吹っ飛び、それら飛散した破砕物がさらなる凶器と化して、インカ兵やスペイン兵の区別無く、そこにいる全ての人々に襲いかかる。
強烈な艦砲攻撃にも耐え得るように築かれた石の砦は、さすがに頑強で、方々で起きた爆発にもかかわらず、屋上階全体が吹き飛ぶまでには至らなかった。
とはいえ、勢いを増して燃え広がる炎を喰い止めることはできない。
「うわぁ!!」
「逃げろぉ!!」
ゴウゴウと燃え狂う火焔と黒煙の海の中で、ついに敵兵たちは、一目散に逃げはじめた。
屋上階の数か所に設けられた、階下へ続く昇降口に向かって、ワッと、スペイン兵たちが我先にと群がっていく。

逃げ遅れてパニックに陥った敵兵たちが、半狂乱の絶叫と共に炎に巻かれていく中、インカ兵や黒人兵たちもまた、緊急避難の態勢に入っていた。
彼らは、あらかじめ用意していた多数の縄梯子を海側手すりに縛りつけ、それを伝って、大急ぎで石壁をくだっていく。
とはいえ、苛烈な炎が迫りくる手すりに結び付けられた縄梯子など、いかに丈夫な太縄であろうとも、実に儚い短命なものである。
その上、逆に、炎が梯子を伝い降りてくる危険もある。
それ故、多くの兵は、梯子にたよらず、自らの手足を使って石壁を大急ぎで降りながら、石壁途上に幾つも設置された覗き窓を目指した。
登り来る時は、全ての窓が固く閉ざされていたが、今は、幾つかの窓が、大きく開け放たれている。
マルセラによって解放された鉄窓から先に侵入していたインカ兵たちが、彼らを撃退しようとする敵兵と戦いながら他の窓も次々と開け放ち、屋上階から下りくる友軍の兵たちを砦の内部へ誘導していたのだった。
今や、その砦内は、もともと砦内にいたスペイン兵はもとより、屋上階から避難してきたスペイン兵たち、さらには屋上階から避難して窓から雪崩れ込んだインカ兵や黒人兵も加わって、ひどい満杯状態になっていた。
その密集した砦の内部で、はやくも両軍の激しい白兵戦が開始されていたのだった。

一方、その頃、アンドレス自身は、まだ赤黒い炎の燃え盛る屋上階にいた。
アンドレス、そして、アレッチェ、二人は今も対峙し合ったまま、その場を動かずにいる。
正確には、両者共に全く隙が無く、まるで剣士が間合いを取りながらジリジリと睨み合っているかのように、動きの取りようがなかったのだ。
その間にも、炎は怒涛のごとく猛威を奮い、毒素を含んだ煙や熱風が吹き荒れて、息することさえ苦痛なほどだった。
それでも、アンドレスの手にある拳銃の銃口は、まるで銃そのものが意志を持っているかのように、ピタリ、とアレッチェに狙い定められたままである。
アレッチェを睨み据えて微動だにせぬアンドレスの双瞼は、周囲で逆巻く赫熱(かくねつ)の焔を映して轟々と燃え上がっていた。
「アレッチェ――!
投降しろ!!
でなければ、今すぐ、おまえを撃つ!」

かたやアレッチェは、舞い散る金色の火の粉を黒髪に被りながら、仮面のような酷薄な表情を変えることなく、ズイッ、と一歩をアンドレスの方へ踏み出した。
「ほう、面白い。
そのような屁っ放り腰で、わたしが撃てるのか?」
その刹那、中央昇降口の鉄扉の陰から、アンドレスの方に向けて、猛烈な勢いで球状の物体が投げ込まれた。
それは、またもアレッチェの暗黙の合図によって、敵兵が投げつけた手榴弾であった。
先刻の不意打ちの銃撃で、その可能性を予測していたアンドレスの心眼と鍛えられた動体視力は、反射的に、彼をその場から飛びのけさせていた。
彼の周囲のインカ兵たちもまた、同様に、瞬時にその場から飛びすさる。
手榴弾とはいえ、この時代のものは、まだ導火線から着火する原始的な小型爆弾にすぎない。
それでも、原油の中に投げ込まれた小爆弾の威力は強烈だった。
耳を聾する爆破音と共に派手に爆発して、屋上階を吹き飛ばさないまでも、頑健な石床を深く抉(えぐ)り、破砕物を辺り中に撒き散らす。
数メートル先まで跳躍して身を伏せたアンドレスの体は辛うじて難を逃れるも、飛散する手榴弾の破砕物が凄まじく、すぐには頭を上げることすらできない。

数秒の後、歯噛みしながらアンドレスが飛び起きた時には、アレッチェの姿は、既に昇降口の扉の陰まで進んでいた。
「それが、本物の爆弾というものだ、アンドレス。
それも、ごく小型のな。
おまえたちの『小麦粉爆弾』とは、少々、違いがあろう」
天まで焼き尽くさんばかりの激烈な炎と黒煙の厚い壁の向うで、冷笑を湛えたアレッチェの唇がそう動くのを、アンドレスは確かに見た。
「アレッチェ…!!」
アンドレスが千切れるほど強く唇を噛み締めた時には、アレッチェの姿は、鉄扉の向うへ完全に消えていた。
と同時に、ガーンッ、と重々しい音がして、扉が勢い良く閉ざされる。
はっと瞬時に見渡せば、屋上階の全ての昇降口の鉄扉が固く閉じられ、恐らく、既に内部から施錠されているものと思われた。
屋上階に燃え広がった炎や煙が階下にまで伝い降りていかぬよう、それは防火扉の役割も果たしているのだ。

「待て――!!
アレッチェ――!!!」
鉄扉に向かって半狂乱で走り出そうとしたアンドレスを、ジェロニモが、背後から、ガッシ、と猛烈な力で押さえ込んだ。
「アンドレス様、ダメです!!
あの扉から、俺らは中には入れません!!
それより、早く、俺たちもここから脱出しないと、炎に巻かれちまいます!!
手すりに結び付けた縄梯子だって、すぐに焼け切れちまいますよ!!」
ジェロニモの声が聞こえているのかいないのか、アンドレスは、殺気立った眼をギリギリ見開いて血走らせている。
そんな彼を、ジェロニモは数名の巨体のインカ兵と共に引き摺るようにしながら、手すりの方へ連れ戻していく。
「アンドレス様、気を確かにしてください!
さあ、ここを下りますよ。
この縄梯子は、いつ燃え切れるか分かりません。
だから、梯子に頼らず、自分の手足で石壁を下りるつもりでくだってください。
手元、足元をしっかり!!」
アンドレスの目を真直ぐ覗き込んで、強い口調で言うジェロニモの厳しい声に、アンドレスは、やっと我を取り戻した。
そんなアンドレスに、ジェロニモが、少し声音を鎮めて、畳み掛けるように続ける。
「まずは、壁を途中まで下りて、仲間たちが開け放ってくれた覗き窓から、急いで俺たちも砦の内部に入りましょう。
そして、アレッチェを追いましょう!
奴は、まだ、この砦の中にいるはずです」
降り注ぐ紅い火の粉を被りながら、己を護るようにして縄梯子に自分を導いてくれているジェロニモ、そして、周囲のインカ兵たちに、アンドレスは瞳の険しさを和らげ、悲しげに頷いた。
「ああ…取り乱してすまない……。
多くの仲間たちを…撃たれてしまったな」

そんなアンドレスにジェロニモたちも目を伏せて頷き、眼前の若き将の、微かに震える、それでいて炎のように熱い肩に触れた。
「アンドレス様の気持ちは、分かりすぎるほど分かっていますよ。
それは、俺たちだって――。
さあ、皆の仇を取るためにも、ともかく今は急ぎましょう!」